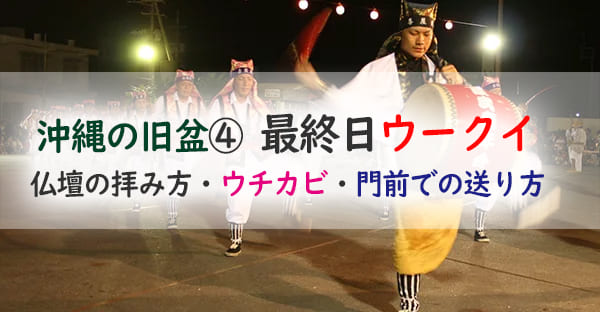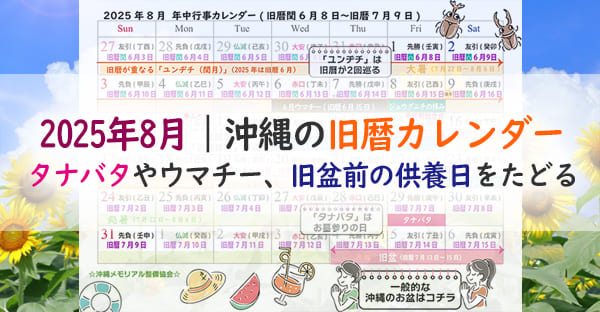お彼岸におはぎ・ぼたもちを作ろう|由来と簡単レシピ、親子で楽しむ行事食

お彼岸になると、多くの家庭でお仏壇やお墓に「おはぎ(ぼたもち)」を供える習慣があります。
けれども「お彼岸のおはぎはいつ食べるの?」「春と秋で呼び名が違うのはなぜ?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、おはぎをお彼岸に供える由来や意味、春彼岸と秋彼岸での呼び名の違い、さらに親子で作れる簡単レシピをご紹介します。最後に沖縄のお彼岸の特徴についても触れ、全国との違いもわかりやすく解説します。
目次
お彼岸とおはぎ・ぼたもちの関係

お彼岸の時期にお仏壇やお墓へ供える定番といえば「おはぎ(ぼたもち)」です。
ご先祖様に感謝を伝える供養の一つとして供えられ、家族で食べることでご縁を深める意味も込められています。特にお彼岸は「彼岸=あの世」と「此岸=この世」が最も近づく時期とされ、ご先祖様を想う心を食文化として表す大切な行事食なのです。
おはぎとぼたもちの違い
「おはぎ」と「ぼたもち」は同じ食べ物を指しますが、呼び名が季節によって変わります。
春のお彼岸では、春の花である牡丹にちなんで「ぼたもち」と呼び、秋のお彼岸では萩の花になぞらえて「おはぎ」と呼ぶのが一般的です。
材料や作り方に大きな違いはなく、季節を感じさせる呼び分けが伝統として受け継がれてきました。
小豆を使う意味
おはぎのあんこに使われる小豆には、赤い色が「魔除け」になるという意味があります。
古くから赤色は邪気を払うと信じられており、ご先祖様への供養や家族の健康を願う心が込められてきました。甘い小豆あんで包んだおはぎを供えることは、ご先祖様への感謝と家族の無病息災を願う象徴的な習慣なのです。
お彼岸のおはぎはいつ食べる?

お彼岸におはぎを供える時期は、厳密に決まっているわけではありません。
一般的には「彼岸の入り」から「彼岸明け」までの7日間であれば、いつお供えしても問題ありません。ただし、多くの家庭では春分の日・秋分の日にあたる「中日(ちゅうにち)」に合わせておはぎを供え、家族でいただくことが多いようです。
お供えしたおはぎをその日のうちに皆で分けて食べることは、ご先祖様とのつながりを感じられる大切な習慣といえるでしょう。
・沖縄の秋彼岸2025年はいつ?シルバーウィークの日程とお供え・拝み方
春はぼたもち、秋はおはぎ
春のお彼岸に供えるものは「ぼたもち」、秋のお彼岸に供えるものは「おはぎ」と呼び分けられています。
これは食材や製法の違いではなく、季節の花にちなんだ呼び名の変化です。春は大きく華やかな牡丹の花に見立てて「ぼたもち」、秋は野に咲く萩の花に重ねて「おはぎ」と呼ばれるようになりました。
こうした言葉の使い分けには、四季の移ろいを大切にしてきた日本人の感性が表れています。
おはぎの簡単レシピ

おはぎは特別な調理道具がなくても作れる、家庭向けの行事食です。基本の手順を押さえれば、親子で一緒に楽しく挑戦できます。
基本の材料と下ごしらえ

おはぎ作りに必要な材料は、とてもシンプルです。
特別な食材を買いそろえる必要はなく、普段のご飯作りで馴染みのあるものばかりなので、気軽に挑戦できるのも魅力です。家庭にある材料で手軽に作れるからこそ、親子で一緒に調理を楽しむ行事食として受け継がれてきました。
● あんこ(こしあん・つぶあんは好みで選ぶ)
● 塩(甘さを引き立てるために少量)
これらの材料をそろえたら、まずはご飯の準備から始めます。もち米とうるち米を合わせて洗い、30分ほど水に浸してから炊飯器で炊き上げます。
あんこは手作りすることもできますが、市販品を利用すれば短時間で仕上がり、忙しい時期でも無理なく取り入れることができます。
作り方の手順

おはぎ作りは一見むずかしそうに思えますが、実際にはシンプルな流れで仕上げられます。
子どもと一緒に作業できる工程も多いので、家族の会話を楽しみながら調理できるのが魅力です。きちんと手順を踏めば、見た目も味も本格的なおはぎが完成します。
② 手を水でぬらし、適量を丸めて俵型に整える。
③ あんこをラップに広げて丸めたご飯を包み、形を整える。
④ 表面がなめらかになれば完成。
これらの工程を順番に行えば、誰でもきれいなおはぎを作ることができます。
特に「丸める」「包む」といった工程は子どもが楽しんで参加できる部分ですので、親子で分担しながら仕上げると良い思い出になるでしょう。
アレンジレシピ

おはぎは基本のあんこで作るだけでも十分においしいですが、少し工夫することで味のバリエーションを楽しむことができます。
家庭の好みや子どもの好き嫌いに合わせてアレンジできる点も魅力です。行事食でありながらおやつ感覚でも味わえるので、幅広い年代に喜ばれるでしょう。
● ごまおはぎ:すりごまや黒ごまを混ぜた砂糖をまぶす。
● ずんだおはぎ:枝豆をすりつぶして砂糖と塩を加えたずんだあんで包む。
これらのアレンジを取り入れることで、彩りが豊かになり、食卓も華やぎます。
家族や友人が集まる場ではいくつかの種類を作り分けると、選ぶ楽しみも加わって一層盛り上がるでしょう。お彼岸のお供えとしてだけでなく、季節のおやつとしても役立ちます。
あんこ団子で手軽にアレンジ

お彼岸のお供えやおやつには、おはぎ以外に「あんこ団子」もおすすめです。
市販の団子粉を使えば短時間で作れ、もち米を炊く手間がないため気軽に挑戦できます。小さなお子さんでも丸めやすく、食べやすい一口サイズに仕上がるのも魅力です。
② 一口大に丸め、熱湯でゆでて浮き上がったら冷水にとる
③ 串に刺して盛り付け、たっぷりのあんこをのせれば完成
お団子は形をそろえる必要がないため、親子でわいわい作っても楽しいものです。
茶碗蒸しや煮物のように和の食卓にもよく合い、お供えした後に家族でいただくと季節の風情をさらに感じられます。
あんこを包むときのポイント

おはぎ作りでつまづきやすいのが、あんこでご飯をきれいに包む工程です。
ベタつきやすかったり、あんこが破れてご飯がのぞいたりと、ちょっとしたコツが仕上がりを左右します。作業前に道具と手元を整え、温度と水分をうまくコントロールすると、見た目も味もぐっと安定します。
● ご飯は熱々を避け、人肌まで粗熱を取ってから丸める(ベタつき防止)
● 手は水で軽くぬらすだけにし、濡らし過ぎない(あんこが滑らないように)
● ご飯は小さめ(目安25〜30g)にして俵形に整え、合わせ目を下にして置く
● あんこの厚みは均一に(目安2〜3mm)。薄すぎると破れ、厚すぎると重くなる
● 仕上げはラップ越しに軽く転がして面をならし、乾燥防止に濡れ布巾をかける
これらを意識するだけで、割れやベタつきが減り、つやのある仕上がりになります。親子で作る場合は、「ご飯を丸める係」「ラップで包む係」と役割を分けるとスムーズです。少し小さめサイズで数を作ると、見た目も可愛く食べやすくなります。
小豆とあんこの豆知識

おはぎの主役である小豆は、実は家庭でも扱いやすい食材です。
戻し不要で煮られ、砂糖の入れ方次第で日持ちや風味が変わります。手作りが難しい日は市販品を賢く活用してもOK。味の決め手は「渋みの抜き方」と「甘さの入れ方」にあります。
…小豆はたっぷりの水で沸騰→一度ゆでこぼして渋みを抜く/新しい湯でコトコト弱火。皮が割れにくいよう差し水で温度を急に上げない/塩は仕上げ直前にほんのひとつまみ(甘さを引き締める)
● 甘さの調整・保存
…砂糖は数回に分けて加え、休ませながら含ませるとツヤが出る/煮詰めすぎたら湯でゆるめる/粗熱を取って保存容器へ。冷蔵3〜4日、冷凍約1か月が目安(小分け冷凍が便利)
● 代用品・バリエ
…時間がない日は市販のこしあん・つぶあんで時短/彩りに白あん・ずんだ・かぼちゃあん・さつまいもあんもおすすめ/砂糖控えめにしたい場合はあんこの量を少なめにし、表面にきな粉や黒ごまで香ばしさをプラス
手作りあんこは香りが豊かで、炊き上がりの色艶もごちそうの一部です。時間に余裕がない日は市販あんこを使い、翌年は手作りに挑戦するなど、無理のないやり方で続けるのがいちばんです。
親子で楽しむお彼岸行事

おはぎ作りは、家族で同じ鍋を囲みながら「ご先祖さまに手を合わせる心」を自然に伝えられる行事です。
台所で交わす会話や、でき上がりを褒め合う時間そのものが供養につながり、子どもにとっては記憶に残る体験になります。前日にあんこを用意し、当日は丸める・包むに集中すると、慌ただしい彼岸の期間でも無理なく楽しめます。
子どもと一緒にできるポイント
親子で作るときは、「失敗も味のうち」という気持ちで楽しむのがコツです。
大人が下ごしらえを担当し、子どもは“形づくり”や“見た目の仕上げ”など達成感のある工程を任せると、最後まで集中して参加できます。安全面だけ先に声がけしておけば、年齢に合わせて役割分担がしやすくなります。
● ラップの上でコロコロ転がし、表面をなめらかにする“仕上げ係”を担当
● きな粉・黒ごま・ずんだなど、表面の味付けや盛り付けを子どもが選ぶ
● 数を数える・容器に並べるなど、低学年でもできる“お手伝いタスク”を用意
● 熱いご飯は大人が扱い、子どもは冷ました生地のみを担当するなど温度で役割分け
作業は短い区切りで褒めながら進めると、最後まで楽しく続けられます。でき上がったおはぎをお仏壇にお供えし、「いただきます」の前に一言手を合わせる流れまで体験できると、行事の意味がぐっと身近になります。
食育としてのおはぎ作り
行事食を一緒に作ることは、ただの料理体験ではありません。季節や行事の意味を知り、食べ物ができるまでの手間や、作ってくれた人への感謝を学ぶ良い機会になります。計量や段取り、衛生面の意識づけなど、生活に役立つ学びがぎゅっと詰まっています。
なぜ彼岸におはぎを供えるのか、呼び名の違い(ぼたもち/おはぎ)を通じて四季や日本の行事に触れる
● 感謝を学ぶ:
いただく前に手を合わせる体験で「作る人・育てる人・ご先祖さま」への感謝を言葉にできる
● 段取りと衛生:
手洗い→計量→下ごしらえ→盛り付けの順序や、清潔に作る習慣が身につく
● 数・重さの学び:
計量スプーンやキッチンスケールを使い、算数の感覚を実体験で覚える
● 家族の会話:
好みの味や思い出話をきっかけに、世代を越えたコミュニケーションが生まれる
行事の意味がわかると、子どもは「作って供えて食べる」人属きの流れに誇らしさを感じます。無理のない範囲で毎年続けることで、家庭ならではの“わが家の彼岸”という温かな記憶が積み重なっていくはずです。
・子どもに伝えるお彼岸|意味や由来、やさしい説明と昔ながらの風習
沖縄のお彼岸と全国との違い

沖縄のお彼岸は、本州のように「お墓参り+おはぎ」が主流ではなく、家の中でおこなう家拝み(イエウガミ)と、屋敷を守る神々へ感謝を捧げる屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)が中心です。
まずヒヌカン(火の神)に報告し、仏壇(祖霊神)へ拝み、その後に屋内外の神々を巡るという流れが一般的。家庭や地域差はありますが、「家の中で丁寧に整え、感謝を伝える」ことに重きが置かれます。
また、沖縄では重箱料理や果物など“膳を整える”供え方が基本で、おはぎは本来の必須供物ではない点も全国との違いです。
近年は全国的な習慣の影響で柔軟に取り入れる家庭も増えていますが、まずはそれぞれの家の作法を尊重するのが安心です。
・沖縄でお墓参りに行く時期はいつ?昔と現代における違いも詳しく解説
沖縄のお供え物の特徴
沖縄のお彼岸では、神々ごとにふさわしいお供えを整え、順番を守って拝みます。
仏壇には家族が囲める御膳を、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)でも供物を整えますが、屋敷の神々には持ち運びやすい膳やビンシーにまとめ、“整えて巡る”のが基本スタイルです。
● 仏壇(祖霊神):
御三味(ウサンミ)の重箱、白餅、果物(ナイムン)、菓子などを整えて拝む
● ヒヌカン(火の神):
お酒・水・塩に、御膳の一部(ウチャワキ)を添えて朝いちに報告・感謝
● 屋敷の神々(地域によって仏壇も入る)
果物やお酒、花米(ハナグミ)・洗い米(アライグミ)、白餅、必要に応じてシルカビを膳やビンシーにまとめて巡拝
これらは地域・家筋で細部が異なるため、「親戚のやり方」「これまでの家の流儀」をまず確認すると齟齬が避けられます。
マンションなどで全てを回れない場合は、拝み場所を絞って簡略化しても気持ちがこもっていれば大丈夫です。作法は守りつつも、無理のない続け方を意識しましょう。
沖縄のお彼岸の過ごし方や拝み方、お彼岸時期に行うヤシチヌウグァン(屋敷の御願)ついても、下記コラムで詳しく解説しています。
・沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】
現代の沖縄でのおはぎ
もともと沖縄にはお彼岸におはぎを供える固有の風習は乏しく、本州の影響として広まってきた側面があります。
ただ、今では行事食として親しまれ、家族の嗜好や供物のバランスに合わせて取り入れる家庭も増えています。
● 重箱料理や果物を基本にしつつ、子どもと作った手作りおはぎを並べる
● 高齢のご家族の好みに合わせて、小ぶりサイズやきな粉・ごまなど負担の少ない味に調整
取り入れる場合は、まず家族・親戚の合意を大切に。重箱や果物など沖縄の基本を崩さず、そのうえでおはぎを“家族の楽しみ”として添えると、伝統と現代のいいところを両立できます。
来年以降に向けて写真や作り方のメモを残しておくと、わが家流の彼岸が毎年少しずつ育っていきます。
・沖縄の秋彼岸の過ごし方。2025年はいつ?お供えと地域の違い
まとめ|お彼岸のおはぎ作りで家族団らん

お彼岸のおはぎ(ぼたもち)は、ご先祖さまへの感謝と家族の団らんを結ぶ行事食です。
彼岸入りから明けまでの期間にお供えし、いただくことで、季節のめぐりや先人への想いを日常の食卓につなげられます。親子で丸めたり包んだりする時間そのものが、思い出となり、感謝の心を育ててくれます。
全国的な習慣としてのおはぎを楽しみつつ、地域ごとの作法や家庭の流儀も大切にしましょう。沖縄では家拝みや屋敷の御願が基本で、重箱料理や果物などを整える文化があります。
まずは家族や親戚のやり方を尊重し、そのうえで“わが家流”の一品としておはぎやあんこ団子を添えれば、伝統と今の暮らしを無理なく両立できます。
・沖縄の仏壇掃除完全ガイド|御願・お盆・お彼岸前に整える作法
関連記事
合わせて読みたい




人気記事ランキング
 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説
旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!
【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談
親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ
老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説
【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー
一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは
夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識
ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説
【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③
沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③
カテゴリ