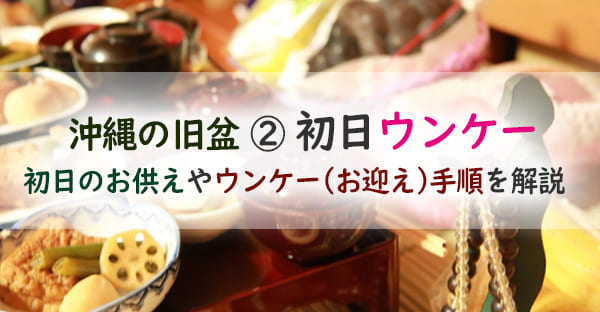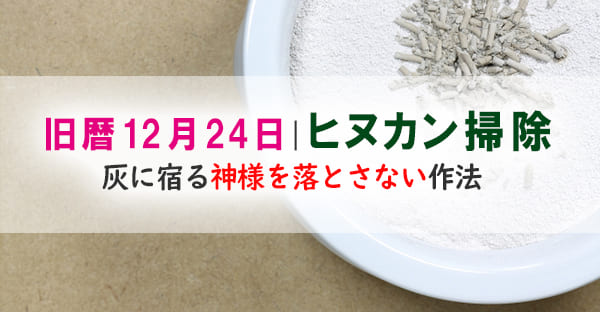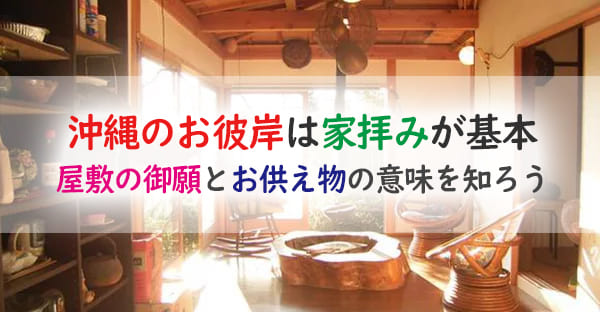【2025年版】冬至(12月22日)はいつ?意味・由来・食べ物・風習をわかりやすく解説

2025年の冬至は12月22日(月)。一年で最も昼が短く、太陽の力が生まれ変わる節目の日です。
古くから「一陽来復(いちようらいふく)」と呼ばれ、運気が上昇に転じる吉日とされてきました。
全国では2025年現代も、かぼちゃや小豆料理を食べ、ゆず湯に入って無病息災を願う風習が残っています。
一方、沖縄では「トゥンジージューシー(冬至雑炊)」を供え、ご先祖や火の神に感謝を捧げる特別な日。
本記事では、2025年度版・冬至の意味や由来、全国と沖縄の過ごし方の違いをわかりやすく紹介します。
目次
【2025年度版】冬至とは?意味と由来をわかりやすく解説

一年で最も昼が短い日
◇2025年の冬至(12月22日)は、一年のうちで昼の時間が最も短く、夜が最も長くなる日です。
この日は太陽の高さが一年で最も低くなり、日照時間が短くなるため、気温もぐっと下がる季節の節目です。
古くから人々はこの太陽の動きを暮らしの基準とし、2025年の冬至のように毎年少しずつ変わる暦の変化を大切にしてきました。
この太陽の動きをもとに作られたのが「二十四節気(にじゅうしせっき)」です。
2025年の冬至はその第22節にあたり、次の「小寒(しょうかん)」までのおよそ15日間を指します。
暦の上ではこの日を境に陽の気が増え始め、季節のエネルギーが少しずつ動き出すとされています。
由来と「一陽来復」の意味
◇冬至の考え方は、中国の古代王朝の暦法に由来します。
太陽の力が最も弱まる日でありながら、翌日から再び昼が長くなることから、「太陽がよみがえる日」として祝われてきました。
その思想が日本にも伝わり、2025年の冬至のように、太陽の力を尊び、季節の変わり目を祈りとともに迎える文化が定着しました。
…「陰が極まり陽に転じる」という意味をもち、冬至を「運気が回復し、再び良い流れが始まる日」としてとらえます。
2025年の冬至もまた、一年の疲れを癒し、新しい光と希望を迎える再生と運気の節目として意識されているのです。太陽のめぐりとともに暮らしてきた日本では、暦の上で冬至を迎えるたびに「生命の再生」と「自然との調和」を感じ取ってきました。
2025年12月22日(月)という日もまた、私たちに“光が戻る瞬間”を教えてくれる大切な一日といえるでしょう。
【2025年版】今年はいつ?日程と暦の関係

◇2025年の冬至(とうじ)がいつか?と言えば、12月22日(月)です。
この日は一年の中で最も昼が短く、夜が長くなる日であり、太陽の力が最も弱まる時期とされています。
冬至は毎年同じ日ではなく、暦や天文の関係によって少しずつ前後します。
ここでは、2025年の冬至の日程と暦とのつながり、そして夏至との違いを詳しく見ていきましょう。
【2025年版】冬至の節気はいつ?12月22日(月)
◇2025年の冬至(12月22日)は、二十四節気のいつかと言えば、第22節の節気にあたります。
この節気は、次の「小寒(しょうかん)」までの約15日間を指し、暦の上では冬の真ん中にあたります。
では2025年前後の冬至の節気はいつだったのでしょう?2024年12月21日、2026年も12月22日が冬至となり、毎年わずかに日付が変わります。
これは太陽の位置と地球の公転軌道が暦と完全に一致しないためで、2025年の冬至の日もその年の太陽の動きによって決定されるのです。
このように、暦と天文の関係から見ても、冬至は“自然と人の暮らしをつなぐ大切な日”として古くから意識されてきました。
冬至と夏至点の違い(昼の長さ・太陽の高さ)
◇2025年の冬至は、太陽の高さが一年で最も低く、昼の時間が最も短くなる日です。
一方で、夏至(げし)は太陽が最も高く昇り、昼が最も長くなる日。
この2つの日は季節の両極にあり、太陽の動きが季節のリズムを作り出しています。
東京を例に取ると、2025年の夏至の昼の長さは約14時間半、冬至は約9時間半で、その差は5時間以上。
太陽の高さの違いが季節の気温や明るさに大きく影響し、自然のリズムを生み出しています。
つまり、冬至と夏至の関係は「日照時間と季節をつなぐバランスの軸」なのです。
【2025年版】冬至の時期に見られる自然の変化(季節の花・空の色など)
◇2025年12月22日前後の冬至の季節は、寒さが厳しくなり始める時期です。
この頃の空は澄み渡り、夕暮れには太陽が低く沈むため、赤や金色に染まる光景が見られます。
植物では、ロウバイ(蝋梅)やサザンカ、ポインセチアなど冬の花が見頃を迎えます。
沖縄では比較的温暖で、トックリキワタなど南国らしい花が咲く頃。
こうした2025年の冬至の季節は、地域ごとに異なる自然の彩りが楽しめる時期でもあります。
太陽の高さや日の長さだけでなく、花や光、空気の冷たさを通して季節の移ろいを感じ取る――
それが、2025年の冬至という日が私たちに教えてくれる自然との関係なのです。
【2025年度版】子どもと食べたい!冬至の行事食とその意味

2025年の冬至(12月22日)には、古くから健康と運気を願って特別な食べ物をいただく風習があります。
寒さが厳しく、太陽の力が弱まるこの季節に、栄養を補いながら新しい運を呼び込む――。
それが、子どもと食べたい2025年の冬至という行事に込められた「食の祈り」です。
かぼちゃ(南瓜=なんきん)を食べる理由
◇2025年の冬至の行事食として欠かせないのが、かぼちゃ(南瓜=なんきん)です。
「なんきん」の“ん”には「運」を呼び込む意味があり、昔から縁起物とされてきました。
本来、かぼちゃは夏の野菜ですが、長期保存ができるため、冬でも食べられる貴重な食材でした。
ビタミンAやカロテンが豊富で、風邪予防や免疫力アップにも効果的。
寒さの厳しい2025年12月の冬至に、子どもや家族の健康を願ってかぼちゃを食べる習慣が生まれたのです。
さらに、南の「南瓜(なんきん)」という字には「陰から陽へ」「下から上へ」という意味があり、「運気を好転させる食べ物」としても大切にされてきました。
つまり、かぼちゃは2025年の冬至の日に子どもや家族の運を呼び戻す“開運食”なのです。
小豆粥・いとこ煮に込められた厄除けの意味
◇2025年の冬至には、小豆を使った料理を食べる地域も多く見られます。
小豆の赤い色は古くから「邪気を祓う」象徴であり、厄除けの力があると信じられてきました。
そのため、冬至の日には「小豆粥」や「かぼちゃと小豆のいとこ煮」を食べる風習が残っています。
特にいとこ煮は、赤い小豆と黄色いかぼちゃの色合いが太陽を連想させ、運気の再生を願う料理として親しまれています。
2025年の冬至(12月22日)には、いとこ煮や小豆粥を食べながら、無病息災と子どもや家族の健康を祈るとよいでしょう。
赤い小豆が冬の寒さをやわらげ、体の内側から陽の気を呼び込んでくれます。
「ん」のつく食べ物「冬至の七種」で運気アップ

◇冬至に「ん」の付く食材を食べると“運”がつくとされ、これを「運盛り(うんもり)」と呼びます。
代表的な七つの食材が「冬至の七種(ななくさ)」で、なんきん(かぼちゃ)、にんじん、れんこん、ぎんなん、きんかん、かんてん、うんどん(うどん)です。
2025年の冬至に、これらの「ん」のつく食べ物を食べることで、運気が二倍に高まるといわれています。
とくに「ん」が二つ含まれる食材は“ダブルの運”をもたらす縁起物。
子どもや家族で冬至の食卓を囲み、2025年の運気を呼び込む年中行事として楽しむのもおすすめです。
【2025年度版】ゆず湯(柚子湯)に入る理由と正しい入り方

◇2025年の冬至(12月22日)には、かぼちゃと並んで「ゆず湯(柚子湯)」を楽しむ風習があります。
寒さが深まるこの季節、香り豊かなゆずをお湯に浮かべて入ることで、体を温めるだけでなく、邪気を祓い、新しい運を迎える準備を整えます。
ここでは、2025年の冬至にゆず湯へ入る意味や由来、健康効果、正しい入り方を解説します。
ゆず湯に入る由来と語呂合わせ
◇ゆず湯の風習は、江戸時代の銭湯から広まったといわれています。
「冬至(とうじ)」と「湯治(とうじ)」の語呂合わせから、「体を癒やす日」として冬至の入浴が習慣化しました。
また、「ゆず(柚子)」は「融通(ゆうずう)が利く」に通じ、2025年の冬至にゆず湯へ入ることで「健康で柔軟な心身で新年を迎える」という願いが込められています。
さらに、柚子の強い香りには邪気を祓う力があるとされ、古くから禊(みそぎ)や厄除けの行事でも使われてきました。
つまり、2025年12月22日という節目の日にゆず湯に入ることは、身体を清めて運気を高める日本古来の風習なのです。
風邪を引きやすい冬・日本の「湯治」
◇昔の日本では、冬至の日に入浴すること自体が特別な行事でした。
「湯治(とうじ)」とは、お湯で体を癒やし、健康を回復する行為のこと。
現代のように毎日お風呂に入る習慣がなかった時代、2025年の冬至の日に湯に浸かることは、一年の疲れを癒やす大切な儀式でした。
ゆずにはビタミンC、クエン酸、リモネンなどの成分が含まれ、血行促進や冷え性改善、リラックス効果が期待できます。
寒さが厳しい2025年の冬至(12月22日)にゆず湯へ入ることで、風邪予防や美肌効果、心身の浄化にもつながります。
昔ながらの「健康祈願の入浴法」として、今も全国の家庭で受け継がれている風習です。
【2025年度版】ゆず湯の入り方とアレンジを紹介!
2025年の冬至にゆず湯を楽しむ際は、まず浴槽に2〜3個のゆずを浮かべてみましょう。
皮に切れ目を入れると香りが広がりやすく、湯気とともにやさしい柑橘の香りが浴室に満ちます。
直接果汁を入れると刺激が強い場合があるため、布袋やネットに入れて湯に浮かべる方法がおすすめです。
最近では、しょうがを加えた「ゆずしょうが湯」や、カモミール・ローズマリーなどのハーブをブレンドする人も増えています。
寒さの厳しい2025年12月の冬至に、家族で香りを楽しみながら入浴することで、心身ともに温まり、穏やかな気持ちで新しい季節を迎えられるでしょう。
【2025年度版】沖縄の冬至「トゥンジー」と全国の風習の違い

2025年の冬至(12月22日)は、日本全国で一年の節目として行事が行われますが、沖縄では少し異なる伝統が残っています。
沖縄の冬至は「トゥンジー(冬至)」と呼ばれ、全国のように柚子湯に入るよりも、祖先や火の神に感謝を捧げる行事としての意味合いが強いのが特徴です。
ここでは、2025年の冬至に行われる沖縄の風習や行事食、そして本州との違いを紹介します。
【2025年度版】トゥンジージューシーと供え方
◇沖縄の2025年の冬至(トゥンジー)では、「トゥンジージューシー(冬至雑炊)」を炊いて供える風習があります。
トゥンジージューシーとは、豚肉や田芋(ターンム)、里芋(チンヌク)などを炊き込んだ雑炊で、家族の健康と繁栄を祈る料理です。
供え物には感謝の言葉を添え、拝みを行った後で家族が一緒にいただきます。2025年の冬至の日も、沖縄の家庭ではこの風習が大切に受け継がれています。
トゥンジージューシーは、太陽の力が弱まる季節に“命の恵みを分かち合う”意味を持ち、沖縄の生活に根づいた行事食といえるでしょう。
【2025年度版】本州との違い|禊・お供え・食文化
◇本州の2025年の冬至(12月22日)では、かぼちゃや小豆を食べて健康を祈り、ゆず湯に入って体を清める風習が一般的です。
これに対して、沖縄のトゥンジーは神々への感謝を中心とした健康祈願の日として伝わっています。
同じ冬至でも、本州が「自分を清める日」であるのに対し、沖縄では「神仏に祈りを捧げる日」として位置づけられているとも言えるでしょう。
また、食文化にも違いが見られます。
本州では「ん」の付く食材や小豆が定番ですが、沖縄では芋類や豚肉、もち米など、地元で採れる食材を使った温かいトゥンジージューシー(芋入り沖縄風炊き込みご飯)が中心です。
2025年の冬至にこうした地域性を感じながら行事を行うことは、日本各地の季節文化を知るうえでも意義があります。
【2025年度版】家族で楽しむアイデア
現代の沖縄では、昔ながらの拝みを守りつつも、家庭の形に合わせてトゥンジーを過ごす人も増えています。
2025年の冬至(12月22日)には、伝統料理を炊いて感謝を伝えるほか、家族で食卓を囲みながら「健康で過ごせますように」と声をかけるだけでも立派な行事になります。
こうした習慣は、地域の気候や風土に合わせて生まれた“生活の知恵”でもあります。
2025年の冬至の日を通して、家族の絆や自然への感謝を感じる時間を持つことが、沖縄の行事の本質といえるでしょう。
2025年の冬至(トゥンジー)は、全国共通の行事であると同時に、沖縄では家族の健康を祈願するウグァン(御願)の日です。
冬至を家族で穏やかに過ごすことは、自然と調和し、季節のめぐりに感謝する心を育ててくれるでしょう。
・沖縄のトゥンジー(冬至)☆本州とは違う行事とは
冬至に込められた運気の意味と「一陽来復」

◇2025年の冬至(12月22日)は、一年のうちで最も昼が短く、夜が長い日です。
この日を境に太陽の力が再び強まり、運気が上向いていくとされてきました。
昔から「冬至は運の節目」とも呼ばれ、季節と運気の関係を意識する大切な行事の日でもあります。
ここでは、2025年の冬至に込められた意味や、一陽来復にまつわる風習を見ていきましょう。
「陰が極まり陽に転じる」節目の日
◇古代中国の思想では、冬至は「陰が極まり、陽に転じる日」とされていました。
太陽の力が最も弱まる一方で、翌日からは昼の時間が少しずつ長くなり、2025年の冬至は“再生”の象徴とされています。
太陽が復活するこの時期は、「運の流れが切り替わる節目」。
そのため、古くから人々は冬至を「運が戻る日」「幸運の始まりの日」として祝い、神社や寺では特別な祈願が行われてきました。
2025年の冬至(12月22日)もまた、陽の気が高まり始める日として、前向きなエネルギーを感じる節目となるでしょう。
冬至から始まる新しい運の流れ
◇冬至の翌日からは、太陽が少しずつ長く昇るようになります。
この変化を昔の人々は「太陽の復活」と呼び、運気が動き出す季節の転換点ととらえてきました。
つまり、2025年12月22日の冬至を境に、停滞していた運や気持ちが再び動き出すとされているのです。
日本では、冬至を「一陽来復の日」として吉日とみなし、新しいことを始めるタイミングに選ぶ人も多くいます。
暦の上で季節が動き出すこの時期は、運気の流れを整えるのに最適な期間。
特に2025年の冬至は、五行や暦の配置から見ても、エネルギーの転換点といえるでしょう。
「一陽来復」のお守りや風習
◇「一陽来復(いちようらいふく)」とは、“悪いことが続いた後に幸運が戻る”という意味の言葉です。
太陽が再び昇り始める冬至の頃にぴったりの言葉で、2025年の冬至(12月22日)にも各地でこの祈りが込められた行事が行われます。
…金運や仕事運、家運を高めるとされ、毎年多くの人がこのお守りを求めて参拝します。
また、京都や奈良の寺社でも冬至祭や祈祷が行われ、運気の上昇と再生を願う風習が残っています。
こうした一陽来復の行事には、「光が戻る」「新しい日が始まる」という自然への感謝が込められています。
2025年の冬至を通して、自分の中の陰と陽のバランスを整え、次の季節に向けて心を切り替えることが、古くからの暮らしの知恵といえるでしょう。
冬至の起源と中国的な思想のつながり

古代中国の暦とはじまり
◇2025年の冬至(12月22日)の起源は、古代中国の暦法にあります。
中国では紀元前の時代から、太陽の動きを観測して季節を定める二十四節気が作られ、冬至は「一年のはじまり」として最も重要な天文学的行事とされてきました。
この暦では、太陽の力が最も弱まる冬至を“陰の極”と考え、翌日から陽の力が増すとされていました。
2025年の冬至の日もまた、古代の知恵を今に伝える節目といえます。
中国的な思想が日本文化に与えた影響
陰陽の思想を重んじる中国的な世界観は、日本の暦や行事にも大きな影響を与えました。
太陽の復活を祝う考え方が伝わり、日本では「一陽来復」という言葉で運気の再生を表すようになります。
この思想は、季節の移ろいを大切にする日本の文化的・宗教的背景と融合し、冬至が「光と再生」を象徴する行事へと発展しました。
2025年の冬至を意識して過ごすことは、古代中国から続く暦の知恵を現代的に感じる機会となるでしょう。
冬至の行事食レシピと暮らしに活かすアイデア

2025年の冬至(12月22日)には、全国各地で家庭的な行事食が作られています。
ここでは、代表的な2つの冬至レシピを紹介します。
どちらも健康と運気を整える実用的な家庭料理で、季節の節目にぴったりです。
小豆と南瓜のいとこ煮レシピ
◇冬至の定番といえば「いとこ煮」。
小豆と角切りのかぼちゃ(南瓜=なんきん)を甘辛く煮た料理で、2025年の冬至の行事食として全国で親しまれています。
小豆の赤は邪気を祓い、かぼちゃの黄色は太陽を象徴する色。
二つの色を合わせて煮ることで、「陰」と「陽」のバランスを整える意味があるとされます。
栄養満点で日持ちもよく、実用的で家庭的な冬至の料理としておすすめです。
体を温める小豆粥レシピ
◇もう一つの定番が「小豆粥(あずきがゆ)」。
米と小豆を一緒に炊くシンプルな料理ですが、寒い季節に体を温める効果があり、2025年の冬至(12月22日)の朝食にぴったりです。
小豆の香りにはリラックス効果があり、冬の疲れを癒やしてくれるのも魅力。
一年の健康を願いながらいただくことで、冬至の行事を生活の中で自然に楽しめます。
まとめ|2025年の冬至は感謝と祈りで新しい季節を迎えよう

2025年の冬至(12月22日)は、太陽の力がよみがえる節目の日です。
かぼちゃや小豆、ゆず湯などの行事を通して、健康と運気を整える意味があります。
沖縄ではトゥンジージューシーを供え、神仏へ感謝を捧げる風習も受け継がれています。
一年の終わりに自然の恵みへ感謝し、家族で穏やかに過ごすことで、
2025年の冬至の日を「一陽来復」――新しい運気が始まる日として迎えられるでしょう。
関連記事
合わせて読みたい


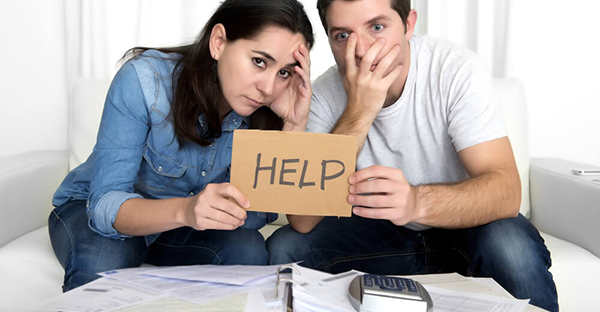

人気記事ランキング
 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説
旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説
【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法
旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール
2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点
お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法
お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説
【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは
自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】
沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識
【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識
カテゴリ