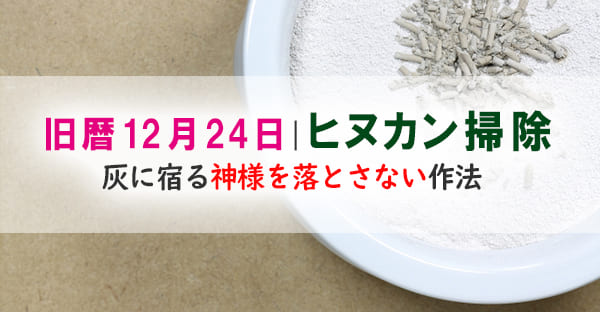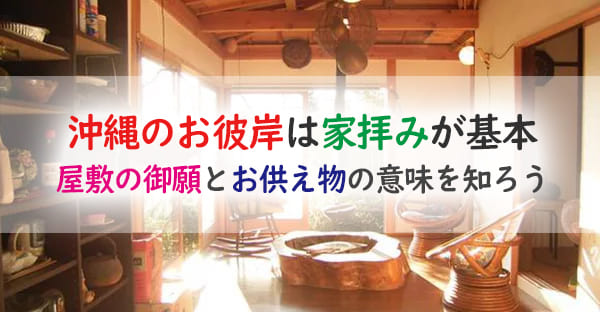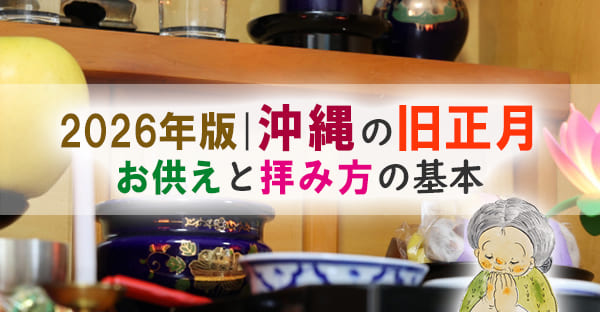沖縄の仏壇掃除完全ガイド|御願・お盆・お彼岸前に整える作法

初めての沖縄の仏壇掃除は不安ですよね。沖縄ではイエウガミ(家拝み)の文化が根づいているため、特にお彼岸やお盆(旧盆)などの旧暦行事では、掃除そのものが拝みの準備になります。
ウグァン(御願)・お盆・お彼岸の前に、何をどこまで整えるのか——迷いがちなポイントを一つずつ整理しましょう。
このガイドでは、最初の一礼と「お断り」から道具の選び方、正しい手順、素材別ケア、香炉の灰の扱い、やりがちなNG、さらに(余裕があれば)ヒヌカンまわりまでをわかりやすく解説。マンションでも無理なくできるコツを交え、短時間で「拝める状態」に整えます。
目次
沖縄の仏壇掃除の基本(目的・頻度・時期)

沖縄では、掃除は拝みに入る前の大切な準備です。
行事前に仏壇まわりを整えておくことで、当日の御願(ウグァン)が落ち着いて進み、供物や線香の配置も乱れません。まずは「いつ整えるか」と「日常はどこまでやるか」の基準を家族で共有しておきましょう。
日常は乾拭き中心で十分です。水分や洗剤を使うのは最小限にして、素材を傷めないことを最優先にします。行事直前は“見える面”を優先して整え、奥の掃除は余裕のある日に回すと続けやすくなります。
・沖縄の秋彼岸の過ごし方。2025年はいつ?お供えと地域の違い
・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー
行事前に整えるタイミング(春彼岸/旧盆/秋彼岸/七夕)
行事前の掃除は、1~3日前に「整え掃除」をするのが目安です。
直前にすべてを詰め込まず、段取りを決めて短時間で仕上げると失敗が減ります。優先順位は「外観→拝む動線→供物スペース」の順がおすすめです。
埃落としとガラス・扉の拭き上げを中心に。供物を置く棚板と花立の水回りを先に整える。
● 旧盆(旧暦7月・ウンケー前):
供物が多くなるため、置き場所の確保と香炉(ウコール)の灰の整えを優先。線香・ロウの補充も同時に。
● 秋彼岸(9月):
夏の湿気で曇りやすい金属仏具を軽く拭き直し。花瓶や受け皿の水ジミもチェック。
● 旧暦七夕(お盆前の準備日):
旧盆に向けた“前倒し整え”。位置の記録(スマホ撮影)→埃払い→ガラス→仏具の順で軽く通す。
行事の意味や拝み方は、地域・門中・家筋で細かな作法が異なります。
たとえばヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の巡る順(春と秋で逆回りの地域あり)、線香の本数や簡略化の可否、ウチャヌク(白餅)の数・置き方、旧暦七夕に掃除する範囲などは家ごとの決め事が残っています。
初めての場合は、過去の写真やメモを確認し、年長の親族に一言相談してから進めると齟齬を避けられます。迷ったら「今年は基本形→来年微修正」の方針で、家の流儀を尊重しましょう。
日々&半月に一度の「軽い整え」
毎日のように大掃除をする必要はありません。日々は5分のルーティン、半月に一度のミニ整えを決めておくと、行事前の負担がぐっと減ります。家族で役割分担を決め、「誰が・どの頻度で・どこまで」を共有しましょう。
正面の埃を軽くハタキ→花立の水替え→供物の傷み確認→落ち灰のひと払い。
● 半月に一度:
扉・棚板の乾拭き→ガラスの曇り取り→金属仏具をから拭き→香炉の灰の高さを整える。
● 月1の見直し:
線香・ロウ・マッチ等の補充、供物用トレイや敷物の点検。
軽い整えは乾拭き最優先が基本。水分はシミや反りの原因になるため最小限にし、使ったらすぐに乾拭きで仕上げます。
・【沖縄の御願】ヒヌカン(仏壇)への毎月の拝み方
掃除前の準備と心構え(合掌・お断り・環境づくり)

掃除は拝みの前段です。まずは環境・所作・道具を整えてから始めましょう。以下の3点に分けて要点を確認します。
環境づくりと段取り(記録・換気・湿度)
◇作業の前に、いまの配置を写真で記録し、戻し違いを防ぐのが基本です。
埃が舞うので軽く換気し、拭き跡や曇りが出にくい湿度の低い時間帯(できれば午前)を選びます。全体の流れは「短時間で整える→当日に乱れない」をゴールにすると続けやすくなります。
● 窓を少し開けて換気、マスク着用で埃対策
● 湿度の低い時間帯を選び、拭いた後は必ず乾拭きで仕上げる
● 落ち灰受けに新聞・不織布を敷き、火気まわりの安全を確認
撮影データは戻しの強い味方です。線香・ロウ・位牌・遺影の位置関係など、細部ほど後で役立ちます。迷ったら乾拭き最優先・水分最小限を徹底し、線香の扱いは〈線香の本数・作法〉へ誘導すると親切です。
始める前の一礼と“お断り”(家拝みの所作として)
◇手洗いを済ませ、正面に立って静かに一礼します。
はじめにお断り(これから触れますのお知らせ)を伝えると、作業の所作が整い、家族内の共有ルールにもなります。言葉は丁寧であれば十分で、声に出しても心の中でも構いません。
● 位牌・仏具に触れるときは小声で「失礼します」と添える
● 終了時は再度一礼し、「整えが済みました。ありがとうございます」と感謝を伝える
儀礼的に難しい言い回しは不要です。「始めに一礼→お断り→終わりに感謝」の流れを家族で統一しておくと、誰が担当しても安心して進められます。
準備する道具(乾拭きが基本)
◇特別な道具は不要です。
家庭にある“柔らかいもの中心”で十分に整えられます。洗剤は点で試す・極薄めが原則で、基本は乾拭き→必要最小限の湿り拭き→すぐ乾拭きの三段階を守ります。
● 綿棒・やわらかブラシ、竹串に薄布を巻いたもの(細部の埃取り)
● 霧吹き+中性洗剤の“超薄め”/乾いたタオル(仕上げ用)
● マスク・手袋、ゴミ袋、下に敷く新聞紙や不織布(落ち灰受け)
● スマホ(配置記録用)、弱粘着の付箋やマスキングテープ(仮印・注意書き用)
道具は“柔らかさ”が命です。研磨剤や強いアルコールは塗装や金属にダメージを与える恐れがあるため避けましょう。洗剤は目立たない箇所で点テストを行い、使ったら必ず乾拭きで水分を残さない——この繰り返しが安全です。
仏壇掃除の手順(全体フロー)

全体は「外側から内側へ」「上から下へ」の順で動くと、二度手間が減って仕上がりが安定します。最初に現在の配置を写真で記録し、供物はいったん下げて作業スペースを確保しましょう。無理に一度で完璧を狙わず、行事前に“拝める状態”まで整えるのが目標です。
● 外側(天・側板・扉)からハタキ→乾拭き→内部棚へと進める
● ガラス・鏡面は超薄めの中性→すぐ乾拭きで拭き筋を残さない
● 仏具はトレイにまとめて移動し、素材別にやさしく拭き上げる
● 香炉の灰は高さを整え(目安:器の1/2~2/3)、燃え残りを確認
● 最後に配置を戻し、供物を整え、手を合わせて完了を報告
以上の流れを守ると、埃の再付着や配置のズレが起きにくくなります。終わり際は、線香・ロウ・マッチの残量チェックまで済ませておくと、当日の拝みがスムーズです。
位牌・遺影の扱い(外す順番/置き方の注意)
位牌・遺影は最小限の移動に留め、必ず順番の記録→仮置き→原位置への流れを守ります。布を敷いた安定した場所に仮置きし、白手袋か清潔な柔らか布で指紋や皮脂の付着を防ぎましょう。
● 仮置きは経机やテーブルに柔らか布を敷き、名前が見える向きで整然と置く
● 戻す際は中央→左右の順、または元の序列に従い、傾きや角度を微調整
● 迷いそうな箇所は弱粘着の付箋で印を付け、戻し違いを防止
扱いの所作が丁寧だと、作業全体の緊張感が和らぎます。最後にもう一度だけ目線を落として一礼し、整え終えたことをお伝えしましょう。
仏具・器の洗いと拭き上げ(素材に合わせる)
仏具は乾拭き最優先が基本です。汚れが気になる場合のみ“超薄め中性→すぐ乾拭き”の順で、洗剤は目立たない場所で点テストをしてから使います。研磨剤や強いアルコールは塗装・メッキを傷めるため避けてください。
から拭き→超薄め中性→すぐ乾拭き。研磨は最小限、メッキ部は不可
● 木部・漆・金箔調:
乾拭きのみが原則。水分はシミ・反りの原因に
● ガラス・花立:
ぬるま湯+中性で輪ジミを落とし、きっちり乾拭きで曇り防止
● ろうそく台:
ロウはぬるま湯で柔らかくして除去。金属ヘラ・刃物はキズの原因
● 香炉:
燃え残りを確認し、灰の高さと表面を整える(処分方法は後章で解説)
● 打敷・敷物:
埃を払って陰干し。シミ抜きは目立たない箇所で試す
仕上げに全体を見渡し、指紋や拭き筋を軽く取り除けば完成度が上がります。作業直後は湿度が上がりやすいので、数分の換気で乾きを早めると安心です。
素材別のケア注意点

仏壇・仏具の手入れは、まず「湿気に弱い」「洗剤やアルコールは基本NG」という原則を押さえることが大切です。水分は反りやシミ、メッキ剥がれの原因になりやすく、強い薬剤は塗膜や箔を傷めます。迷ったら乾拭き最優先・水分最小限で進めましょう。
仕上げは必ず乾いた柔らかい布で。作業の合間も換気をこまめに行い、拭き筋や指紋を見つけたらその場で軽く取り去ると、全体の完成度が上がります。素材に不安がある場合は、目立たない場所で点テストをしてから広げてください。
木部・塗り・金箔などデリケート部位の扱い
木地・漆塗り・金箔・金粉蒔絵などは、わずかな水分や摩擦でも傷みが出やすい繊細な部分です。基本は乾拭きに徹し、力を入れず“なでる”イメージで埃を払います。光沢を出したい場合も、専用品以外は使わず、まずは布だけで様子を見ましょう。
● 水分は最小限。どうしても必要な場合は“極うすめ”を点使い→すぐ乾拭き
● 金箔・金粉・蒔絵はこすらない。毛ばたきで埃を落とし、布は当てるだけ
● 漆面は温度・湿度変化に弱い。結露時や高湿度の日は無理をしない
● クリーム類を使うときは必ず点テスト→ごく少量→ムラなく伸ばし残さない
金箔や蒔絵は、一度こすれて剥がれると修復が難しくなります。判断に迷うときは、無理に汚れを落とそうとせず、後日あらためて対応しましょう。詳しいお手入れは〈仏壇クリームの使い方〉に誘導すると親切です。
金属仏具(真鍮など)の手入れ
金属仏具は、手脂や湿気でくもりが出やすい反面、やり方を守れば美しさが戻りやすい素材です。まずは乾拭きで様子を見て、必要時のみ超薄めの中性→すぐ乾拭きの順を守ります。強い研磨はメッキや刻印を傷めるため、基本は避けてください。
● 使用後は必ず乾拭きで水分を残さない(サビ・変色予防)
● 研磨剤は最終手段。メッキ・装飾部には使用しない
● ロウ汚れはぬるま湯で柔らかくして除去。刃物・金属ヘラはキズの原因
● 指紋が付きやすい部位は、作業中だけ綿手袋を使うと仕上がりが安定
磨き込みは“やりすぎ注意”が鉄則です。素材や仕上げに合わない研磨は取り返しがつきません。迷ったら乾拭きに戻り、日々の軽いケアでくもりを溜めない運用がおすすめです。詳しくは〈真鍮仏具の磨き〉も参照できる導線を用意しておきましょう。
香炉(ウコール)の灰——整え方と安全な処分

香炉の灰は、線香を自立させるための「大地」の役割を持ちます。満杯のままにしておくと線香が倒れやすく、燃え残りも混じって見た目も不安定になりがちです。
灰が器の上端近くまで来たら、日付に関わらず整えるのが基本です。作業は必ず完全に冷えた状態で行い、火気と換気に注意しましょう。
灰の高さは、器の1/2〜2/3程度を目安に保ち、表面は軽くならして平らにしておくと、次の拝みがスムーズです。作業前に下へ新聞や不織布を敷き、手袋・マスクで埃やにおい対策をすると安心です。
仏壇・ヒヌカン共通の「満杯時」ミニ手順
◇満杯対応は、短時間で安全に整える「ミニ手順」が便利です。
まずは小さなスプーンや竹べら、ピンセットなど、金属でも先端が鋭すぎない道具を用意し、燃え残りの有無を必ず確認します。水を直接香炉に注ぐと灰が固まって扱いにくくなるため、水かけは厳禁です。
● 取り出した灰は広げて火種・炭化片がないか確認(あれば別皿で完全鎮火させる)
● 香炉の前で線香を3本上げ、「灰を整え・移します」の一言を添えてから作業を続ける
● 香炉に残した灰を軽く混ぜて表面を平らにし、必要量だけ取り除いた灰を戻す
● 余った灰は完全に冷えてから新聞紙で包み、可燃ごみへ(自治体ルールに従う)
この「ミニ手順」なら、見た目と安全性を短時間で回復できます。大量にたまっている場合は、複数日に分けて少しずつ整えると埃が舞いにくく、作法上も丁寧です。
(任意)ヒヌカンの灰の取り分け&「移し」の作法
ヒヌカンの灰は依り代(よりしろ)と考える家筋が多く、全量を捨てずに「種灰」を少量残すのが昔ながらの風習です。
作業の前後に一言挨拶を添え、「移して整えます→整え終えました」と心持ちを伝えると所作が整います。地域差はありますが、作法の一例として左回りで抜き、右回りで納めるという所作を用いる家もあります。
● 香炉の一角を少量残して灰を抜き、燃え残りを確認
● 整えた後、残した「種灰」を起点に右回りで灰を戻し、表面をならす
● 終了後に一礼し、「整えが済みました。ありがとうございます」と感謝を伝える
なお、手順・言葉・回し方は家の流儀が最優先です。初めての場合は、親族のやり方や過去の記録を確認し、今年は基本形、来年に微修正の方針で進めると齟齬を避けられます。
処分マナー(ミハナ・マース/可燃ごみ対応)
処分は完全鎮火・完全冷却が大前提です。屋内での処理は火災予防を最優先にし、においが気になる場合は換気をしながら進めます。
沖縄では、灰を包む際にミハナ(米ひとつまみ)やマース(塩)を添えて清め、半紙などの白い紙に包んだ後、新聞紙で包んで可燃ごみに出す、という実務的なやり方が広く行われています(自治体ルールは要確認)。
● 半紙などの白い紙に少量のミハナ(米)やマース(塩)を添えて包む
● さらに新聞紙や紙袋で二重に包み、可燃ごみへ(自治体の区分・収集日に従う)
● 庭や排水口への直捨ては避ける(近隣配慮・詰まり防止)
大量の灰を一度に処分する場合は、数回に分けて行うと安全で静かに終えられます。不安があれば、家族に声をかけて見守りをお願いするのも良い方法です。
行事前チェック

行事前は「何から始めるか」で迷いがちです。ここでは、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)と仏壇拝みを連続して進める前提で、時系列に確認できるポイントをまとめます。家の流儀を最優先に、無理のない範囲で調整しましょう。
春彼岸・秋彼岸の整え(屋敷の御願と同時進行)

彼岸は拝みの回数も供物も増える時期です。前日までに見える面を整え、当日は合掌→お断り→拝みの流れを切らさない段取りを意識します。
一般的な巡拝順はヒヌカン → 仏壇 → 四隅の神 → 門の神 → トイレの神 → 中陣の神ですが、最優先は各家の作法です。
3日前〜前日の前倒し整え(チェックリスト)
当日を“仕上げだけ”にするため、消耗品の確認と外観のクリンナップを前倒しします。奥の汚れは無理に追わず、余裕のある日に回すのが長続きのコツです。
● 外側・扉・棚板の埃払いと乾拭き(上→下の順)
● ガラスの曇り取り(超薄め中性→すぐ乾拭き)
● 金属仏具はから拭きでくもり除去
● 香炉の灰を器の1/2〜2/3に整える
● 線香・ロウの補充、マッチやライターの点検
● 花立・受け皿を洗って乾拭きし、十分乾かして戻す
この段階で“見える面”だけでも整っていれば、当日は拝みの所作に集中できます。配置写真があると戻し違い・高さ違いをその場で確認でき、家族間の認識もそろいます。迷った箇所は無理に触らず、翌日以降の「追加整え」に回すのが長続きのコツです。
当日朝の仕上げと安全確認(チェックリスト)
拝みに入る前に一礼と“お断り”を添え、火気・転倒など安全面を最初に確認します。前日に作った土台を崩さず、軽い整えで美しく締めましょう。
● ヒヌカンへ報告→仏壇の拝みへ進む
● 供物を整える(果物・菓子・白餅など)
● 線香の本数・ろうそく周りの安全確認
● 最後に全体を見渡し、拭き筋・指紋を軽く除去
当日は足し算ではなく仕上げの日です。前日に作った土台を崩さないことを最優先に、指紋や拭き筋など目につく箇所だけを軽く整えましょう。迷ったら前日の写真を見返し、元の状態へ“戻す”意識で仕上げると、短時間でもきれいにまとまります。
屋敷の御願と合わせる場合(ビンシー準備と巡拝順)

同時進行のコツは、供物をひとまとめにし、巡拝順を見える化することです。先にビンシー(持ち運ぶ膳)を組み、メモ片手に「一筆書き」で巡ると往復が減ります。
・ウチャヌク(白餅)
・ナイムン(果物)少量
・ウサク(お酒)
・花米
・洗い米
・シルカビ(必要箇所のみ)
・線香(ヒヌカン用は多め)
・ライター
・灰受け用トレー
・小さな布
● 巡る順を紙に書いて手元へ
(家の流儀を最優先。マンション等は玄関外向きで兼ねる簡略化も可)
ビンシーを先に組み、順番をメモにして一筆書きで巡れば、往復も混乱もぐっと減らせます。各拝み場で同じ所作を繰り返すと、家族の動きもそろい、子どもも参加しやすくなるでしょう。
・沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】
旧暦七夕(お盆前)の前倒し整え

◇タナバタ(旧暦七夕)は、旧盆を迎えるための前倒し整えの好機です。
ここで土台を作っておくと、ウンケー直前の慌ただしさが大きく軽減されます。大掃除化は避け、乾拭き中心・水分最小限で短時間に仕上げましょう。
1週間前〜前日:土台づくり(チェックリスト)
旧盆当日に乱れないよう、外観のクリンナップと道具・消耗品の再点検を行います。家族と分担すると時間短縮になります。
● ガラスは超薄め中性→すぐ乾拭き
● 香炉の灰の高さを整える
● 打敷の陰干し
● 供物トレイや布の点検
● 線香・ロウ・マッチの在庫確認
この土台づくりができていれば、旧盆当日は仕上げに集中でき、準備のストレスがぐっと軽くなります。
道具や消耗品はすべて一カ所にまとめ、家族と共有しておくと動線がスムーズです。足りない物は早めに補充して、当日の買い出しを避けましょう。
当日:最終整えと確認(チェックリスト)
拝みに入る前に一礼と「お断り」をして、仮置きスペースを確保してから作業します。戻し違い防止のため、付箋や写真で位置を見える化しましょう。
● 仮置きスペースを確保
● 位牌・遺影は最小限だけ動かして拭く
● 戻し違い防止に付箋で印
● 最後に一礼し完了報告
最後に、所要時間や詰まった箇所、翌年に改善したい点を来年の自分へのメモとしてスマホに残しておきましょう。小さな気づきでも翌年の段取りの精度が上がり、準備時間が短縮されます。
・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識
よくあるNGと注意

仏壇掃除で起きやすい失敗は、素材を傷める強すぎるケア、作法上の動かしすぎ、そして安全面のうっかりの三つに集約されます。
原因はシンプルで、①水分・薬剤の使い過ぎ、②位牌・金具の扱い違い、③灰の処理ミス。まずは避けたいポイントを押さえてから作業に入りましょう。
位牌・金具の扱いに注意
◇位牌や遺影は最小限だけ動かすのが原則です。
動かす前に正面・斜めから配置を撮影しておくと、戻し違いを防げます。戻しは“今年は基本形、気づきは来年に微修正の方針が、素材にも作法にもやさしい進め方です。
金具は外し過ぎ・締め直し過ぎが破損につながります。刃物や硬いヘラでのこそぎ取りは厳禁。作業中は柔らか布や手袋で指紋・皮脂の付着を防ぎ、最後に軽く拭き上げて整えましょう。
灰の全捨ては避ける
香炉の灰は、線香を支える土台です。一度に全量を廃棄せず、完全に冷えていることを確認したうえで高さ(目安:器の1/2〜2/3)を整えるのが基本。水を直接かけて鎮火させると固結やにおい残りの原因になります。
なお、ヒヌカンの灰は仏壇の灰とは扱いが異なります。より丁寧な手順が必要なため、次のセクションで詳しく解説します。
ヒヌカン(火の神)まわりの整え

◇ヒヌカン(火の神)の灰には神様が宿っているため、むやみに掃除しないとされます。
そのため昔ながらの風習では、春と秋のお彼岸・旧暦12月24日の年に3回行う「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を進める前に、ヒヌカンの掃除をする流れが一般的です。
神様の依り代となるヒヌカンの灰は、「今日は〇〇(お彼岸など)ですので、掃除をさせていただきます」などと、掃除の理由とお断りを済ませた後、ヒヌカンまわりや灰の掃除を進めましょう。
容器・器の清め(潮水の考え方)
清めは「潮水に浸ける→真水で塩気を抜く→完全乾燥」の流れで行います。
長めに浸けることで穢れまで落としやすくなり、香りの通りも安定します。仕上げでは塩分と水分を残さないことを徹底してください。
ボウル(桶)の水にマースを入れる(目安:耳かきほどの茶さじ3杯)。
海水を使う場合は小さじ3杯程度を加えて調整。
② 浸け置き:
器を2〜3時間ほど静かに浸し、汚れやにおいを落とす。
③ すすぎ:
取り出したら真水で7回すすいで塩気を抜く。
④ 乾燥:
布で水気を拭き取り、陰干しで完全に乾かしてから元の位置へ。
⑤ ステージの整え:
霧吹きに入れた潮水で台を軽く清め→水拭き→乾拭きの順で整える。
仕上げに線香を立て、整え終えたことを一言伝えると所作が締まります。細かな分量や言い回しは家筋のやり方を尊重し、毎年同じ手順に揃えると迷いなく進められます。
ヒヌカンの灰の扱い
ヒヌカンの灰は底にのこる種灰を、ティースプーン3杯ほどの少量を残します。底から取り出した種灰に、ヒヌカンの神様が宿るとされています。
底にある「種灰」を少量残してから整えます。所作の前後で合掌と一言を添えると段取りがぶれません。
日本線香3本(またはヒラウコー半ヒラ)を供え、整える理由を伝える。
②種灰を取り分ける:
底からティースプーン2〜3杯の灰を取り分け、別皿に置いておく。
③残りの灰をこす:
残りの灰はこし器(家庭では金網ボウルでも可)でふるい、不純物を除く。
④灰を戻す:
しっかり乾いた香炉に種灰→こした灰の順で入れ、八分目を目安に表面をならす。
⑤戻りの拝み:
残灰にヒジュルウコー(冷たい線香)または火をつけた線香を立てる。
「移ってください」と一言添え、左回り3回で抜き→右回り3回で供える。
残った灰は完全冷却を確かめ、住環境に応じて処分します。
新聞紙の上に白い紙を置き、その上に残った灰を置いたら、穢れを祓うための米、もしくは塩を少量掛けてから包むと安心です。
最後に拝みの完了を報告して締めると良いでしょう。
まとめ|わが家の作法で整える

仏壇掃除は、拝みに入るための心と場を整える時間です。基本は乾拭き中心・水分最小限・上から下へ、外から内へ。
配置は写真で控えて戻し違いを防ぎ、前日に“見える面”まで整えておけば、当日は仕上げに専念できます。無理に全部を完璧にしようとせず、短い手順でも丁寧に——それだけで印象はぐっと変わります。
位牌や遺影は最小限だけ動かし、所作は静かに。ヒヌカンまわりは一礼とお断りから始め、器は清めて乾かし、灰は種灰を少量残して整える——家の流儀を尊重しつつ、いつも通りの段取りで大丈夫です。
最後は手を合わせ、今日の気づきをひと言メモに残しましょう。今年は基本形、来年に微修正。その繰り返しが、わが家らしい整えを育て、季節の拝みをいっそう心地よいものにしてくれます。
- カテゴリー:
- 仏壇・位牌について、
- 日本の年中行事、
- 沖縄の御願行事について
- タグ:
関連記事
合わせて読みたい




人気記事ランキング
 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説
旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説
【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法
旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール
2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点
お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法
お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説
【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは
自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】
沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】 【2026年版】沖縄の旧正月とは?若水・お飾り・ヒヌカン・仏壇へのお供えと拝み方を解説
【2026年版】沖縄の旧正月とは?若水・お飾り・ヒヌカン・仏壇へのお供えと拝み方を解説
カテゴリ