沖縄のお墓掃除の作法とコツ|拝み方・道具・NG行為まで完全ガイド
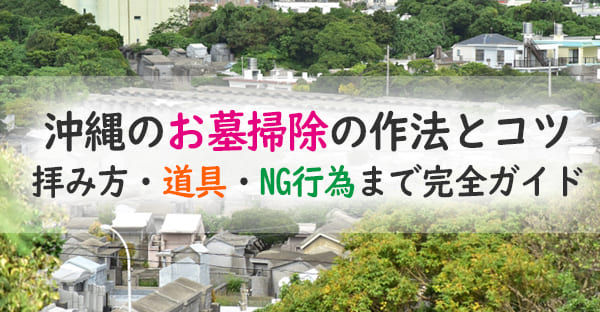
沖縄でのお墓掃除(ハカヌスージ)は、ただの清掃ではなく「ご先祖様との大切な時間」を整える行為として、深い意味を持っています。特に旧盆やシーミー(清明祭)、七夕(タナバタ)などのお墓参り行事の前には、家族総出で墓地の掃除や準備を行う風習が根付いています。
本州とは異なり、沖縄では墓地を自分たちで管理する「個人墓地」が多く、敷地内に土地神様やヒジャイガミ(左神)への拝み所があることも珍しくありません。また、お墓には“後生の通り道”があり、左側から入ってはいけないといった独自の作法も存在します。
この記事では、2025年の行事スケジュールをふまえつつ、沖縄のお墓掃除の基本作法・掃除のコツ・避けたい行動・便利道具などをわかりやすく解説します。掃除する“こと”そのものが、先祖を敬う心のあらわれになる──そんな沖縄ならではの掃除文化をご紹介します。
目次
沖縄のお墓掃除とは?本州との違い

沖縄のお墓掃除には、本州とは異なる文化的背景と独自の作法が息づいています。日本本土では、菩提寺の境内にある家族単位の墓石が一般的ですが、沖縄では広い敷地をもつ個人墓地や一族共有の門中墓(むんちゅうばか)が主流です。
掃除ひとつをとっても、単なる清掃ではなく「神聖な準備の儀式」として、ご先祖様や土地神への敬意を表す意味が込められています。
特に旧盆やシーミー(清明祭)などの墓参り行事の前には、墓地の掃除を通してご先祖を迎える「場」を整えるという意識が強く、ご家族や親族が協力しながら準備を進める光景が見られます。
個人墓地と門中墓が多い沖縄独自のスタイル
沖縄では、「門中(ムンチュー)」と呼ばれる父系血縁集団の単位で共同墓を持つ風習があり、これが門中墓として広く知られています。加えて、各家庭が自分たちで墓地を所有する「個人墓地」も多く見られ、墓地の管理や掃除も基本的に家族や親戚で行います。
● 個人墓地:近年増えている家族単位の墓。掃除やお供えも家庭ごとに行う。
これらの墓では、墓前の拝み方や掃除の段取りにも沖縄ならではの作法があり、たとえば掃除の前に墓の左手に鎮座するヒジャイガミ(左神)に拝むことも大切な“ならわし”です。掃除という行為が、ただの「片づけ」ではなく、神聖な供養の一環であることがわかります。
・沖縄のお墓は正に「家」。琉球墓の5つの魅力とは
沖縄ならではの注意点
沖縄のお墓は、その形状も独特です。かまぼこ型の屋根をもつ「亀甲墓(きっこうばか)」や、戦後に広まった「コンクリート墓」など、本州の墓石墓とは異なる構造が多く見られます。これらのお墓は規模が大きく、掃除する範囲も広いため、しっかりとした準備と段取りが必要です。
また、コンクリート墓や亀甲墓は湿気や高温多湿な気候の影響を受けやすく、カビ・苔・水垢がつきやすいのが特徴です。
強力な洗剤やメラミンスポンジを使うと表面を傷つけてしまうため、掃除の際には素材に合った洗浄方法や専用の道具を選ぶことが大切です。
近年では、草刈り機や高圧洗浄機を活用する家庭も増えていますが、使用時にはコンクリートの劣化や亀裂にも注意が必要です。お墓の形に応じた掃除方法を知ることは、ご先祖様の眠る場所を長く清潔に保つための大切な“心得”とも言えるでしょう。
沖縄のしきたり|拝み作法と通り道

沖縄では、お墓掃除を始める前に「まず手を合わせる」という独特のしきたりがあります。本州では掃除→お供え→合掌といった順序が一般的ですが、沖縄では掃除の前に土地神様やヒジャイガミ(左神)様へ拝む“御願(うがん)”を行うのが基本です。
これは、お墓がご先祖様の「家」であるという意識に根ざしており、掃除を始める前に「これから入らせていただきます」「今日はこのような目的で来ました」と伝えることが、しきたりであり心遣いとされています。
お墓という神聖な空間に足を踏み入れる“こと”そのものが、ご先祖様や神々との対話の始まりとされているのです。
ヒジャイガミ(左神)様への御願
墓地の敷地内に入ったら、まず拝むべきは、お墓の左側(拝む人から見て右側)に鎮座するとされる「ヒジャイガミ(左神)」様です。ヒジャイガミはその土地とお墓を守る神様であり、沖縄の御願文化の中では非常に大切な存在です。
● 火をつけずに立てる「ヒジュルウコー(冷たい線香)」で手を合わせます
● 線香は「タヒラ半(2枚半)」「シルカビ(敷き紙)」を使う地域もあります
掃除を始める前にこの御願を済ませることで、「今日ここで作業をさせていただきます」「ご無礼をお許しください」という意味合いを伝え、神様に一礼するような心持ちで臨むのが沖縄の伝統的なしきたりです。
左側は“後生の通り道”、右側から入るのがマナー
沖縄のお墓では、敷地の左側(墓に向かって左)は「後生(グソー)」――つまりあの世の通り道とされています。そのため、生きている人=イチミ(生身)は左側から入らず、右側から墓地に入るのが古くからのしきたりです。
掃除やお参りの前には、墓地の入口でヒジュルウコーを1枚だけ立て、「今日は清掃のために来ました」と静かに報告する家もあります。そしてそのまま、左側ではなく右側の道を通って墓地へと進みます。
● 生身の人は右側から入るのが礼儀とされる
● 墓地の入口で拝む「入口御願」もかつては一般的だった
このようなしきたりは近年あまり見かけなくなりましたが、沖縄の伝統を大切にする家や地域では今も守られています。たとえ簡略化された形でも、「掃除の前に一礼する」「右側から入る」など、少しの心がけで、供養の気持ちがより深まることでしょう。
沖縄のお墓掃除はいつする?2025年のおすすめ時期

沖縄のお墓掃除は、特定の仏事や季節の節目にあわせて行われるのが一般的です。「掃除だけのために行く」というよりは、ご先祖様への供養とセットで考えられており、お墓参り行事の直前に掃除を行うという習慣が根づいています。
2025年も例年通り、清明祭(シーミー)や旧盆(お盆)、七夕(タナバタ)などが大きな節目となり、多くの家庭がその前にお墓を整えます。「お墓掃除はいつやればいいの?」と迷ったときは、まずこれらの行事予定を確認しておくと良いでしょう。
清明祭・旧盆・七夕(タナバタ)など、旧暦行事と掃除の関係
沖縄では、お墓掃除は「行事の準備」としての意味合いが強く、年に何度か訪れるタイミングに集中して行われます。以下は代表的なお墓参りと掃除の関係です。
● 七夕(旧暦):お盆の案内をする日。2025年は8月29日(金)
● 旧盆(お盆):ウンケー〜ウークイ(迎え火〜送り火)。2025年は9月4日(木)~6日(土)
とくに旧盆の直前には「墓掃除を済ませてからご先祖様を迎える」という考えがあり、旧盆の1週間〜数日前に掃除を行う家庭が多く見られます。七夕(タナバタ)も、ムートゥーヤー(宗家)が事前にお参りするタイミングとして意識され、掃除や草刈りなどの準備がされる時期です。
このように、掃除のタイミングは年中行事に密接に関わっており、沖縄の文化においては「掃除すること=供養の一部」と捉えられているのです。
沖縄と本州のお彼岸は「意味」が異なる?
全国的にお彼岸といえば、春分・秋分を中心とした7日間に行われる墓参り行事として知られています。本州では、故人やご先祖様と向き合う供養の機会として、春秋どちらもお墓掃除や墓参りを欠かさず行う家庭が多い傾向にあります。
一方で沖縄では、もともとお彼岸は仏壇前での供養(家拝み)=イエウガミ、そして家を守護する屋敷の神々へ感謝の拝みを捧げる「屋敷の御願=ヤシチヌウグァン」が中心でした。お墓参りは「清明祭」や「旧盆」など、特定の年中行事で行うものとされ、お彼岸に掃除や参拝をする習慣は一部地域や門中に限られていました。
とはいえ近年では、「秋のお彼岸(フカマチヒングァン)」だけはお墓参りをする家庭も増えつつあります。これは、「春は自然への感謝」「秋はご先祖への感謝」と捉えられているためで、秋分の頃に先祖代々の古い墓(按司墓など)を訪れ、掃除と供養を行う家もあるのです。
沖縄の秋のお彼岸は、2025年は9月20日(土)〜9月26日(金)。ちょうど旧盆(9月4〜6日)と近いため、旧盆後の落ち着いた時期に再び墓掃除と感謝の拝みを行うという流れも自然です。
掃除とお参りのタイミングとしても、意味のある1週間となるでしょう。
2025年の沖縄でおすすめの暦・日取りは?
2025年にお墓掃除を計画するなら、以下のタイミングを参考にすると良いでしょう。
「行事の直前」かつ「天候が安定した日」を選ぶのが基本です。
● シーミー前の週末(3月下旬〜4月第1週):春の気候が安定し掃除しやすい
● 七夕前の週(8月下旬):草木が伸びる時期、草刈りも含めて早めの掃除が◎
● 旧盆直前の土日(8月30日〜31日頃):お供え準備と並行しやすい
● 雨の少ない午前中が理想的:沖縄の夏場は午後にスコールが多いため
また、干支や六曜(仏滅を避けるなど)を気にされるご家庭では、吉日(大安・友引など)や十二支の相性も確認して日程を決めることもあります。
遠方から戻る家族との予定調整や、炎天下を避ける意味でも「早めに掃除だけ済ませておく」という選択肢も有効です。とくに2025年の旧盆は9月と遅めの日程のため、8月中旬〜下旬の涼しい時間帯に掃除を終えておくのがおすすめです。
・沖縄のお墓参りの基礎知識。毎年行われる3つの行事とは
沖縄のお供え物|季節や行事ごとの工夫

沖縄のお墓参りでは、掃除を済ませた後に「お供え」をするのが基本です。特に清明祭(シーミー)や旧盆、七夕(タナバタ)などの節目では、お供え物の内容や供え方にも地域性と季節感が表れます。
掃除とお供えは切り離せないものであり、「場所を清めてから、感謝や祈りを捧げる」という一連の流れは、沖縄における供養文化の大切な“型”のひとつです。ここでは、各行事ごとの定番のお供え物と、供える際の注意点をご紹介します。
七夕や旧盆のお墓参りに欠かせないお供え物とは?
沖縄で「お墓に何を供えるか」は、その行事の意味と深く関わっています。七夕(旧暦7月7日)や旧盆のように、ご先祖様に“これからの予定”や“帰省の時期”をお伝えする拝みでは、「報告」と「感謝」の気持ちを込めた、質素で清らかな品々が選ばれます。
● 日付:2025年は8月29日(金)
● 意味:旧盆のご案内。ムートゥーヤー(宗家)が先祖に報告
● 供え物:ミジティー(お水)、ウチャトゥ(お茶)、ウサク(お酒)、シルカビ、線香(ヒラウコーまたは日本線香)
● 日付:2025年は9月4日(木)~6日(土)
● 意味:ご先祖様を迎え、共に過ごし、送り出す三日間
● 供え物:
・ウンケー(初日)→ ジューシーや簡素な膳(ウンケージューシー)
・ナカヌヒ(中日)→ ウチャヌク、果物、飲み物など
・ウークイ(最終日)→ 重箱料理(ウサンミ)、豚の三枚肉、かまぼこ、天ぷらなど
旧盆では日によって供える物が変わるため、「何を、どの日に」供えるかを正しく知っておくことが大切です。地域や家によっては、線香の本数や器の並べ方などにもこだわりがあるため、事前に確認すると安心です。
・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識
掃除後に供えるべきもの・避けたいものとは?
お墓掃除を終えたあとのお供えには、「清らかさ」と「ご先祖様への敬意」を意識した品物を選ぶことが基本です。逆に、汚れやすいもの・においが強すぎるものは避けられる傾向にあります。
● ミジティー(湧き水や水道水でも可)
● ウサク(泡盛などのお酒)
● ウチャトゥ(お茶)
● ウチャヌク(餅)や花米(洗い米)
● 季節の果物や旬の野菜
● ヒラウコーやジュウゴフンウコー(線香)
● シルカビ(紙幣形の白紙)
これらは比較的腐りにくく、短時間での供養に向いています。また、お供え後に「ウサンデー(お下がりを持ち帰っていただく)」を行う家庭では、取り分けやすく食べやすいものを選ぶのもポイントです。
● 生魚や傷みやすい揚げ物(夏場は特に注意)
● 臭いが強すぎる食品(ニンニク・ネギ類など)
● 菓子パンや洋菓子(供養としての意味合いが薄れやすい)
また、火の扱いにも注意が必要です。供物の近くに線香やロウソクを立てる際は、風防や受け皿を使うなどして火災を防ぐ工夫も忘れずに行いましょう。
墓石とコンクリート墓、掃除方法の違い

沖縄のお墓は、御影石などの墓石タイプと、戦後に多く建てられたコンクリート墓の大きく2つに分けられます。
それぞれ材質や構造が異なるため、適切な掃除方法や注意点も違ってきます。
間違った掃除をしてしまうと、かえって劣化を早めてしまうこともあるため、正しい方法を知っておくことは非常に大切です。
ここでは墓石とコンクリート墓それぞれの掃除の基本をご紹介します。
墓石掃除の基本|水と柔らかい布で優しく
墓石のお墓は御影石などの天然石が使われており、表面に細かな目地や彫刻があるためデリケートです。掃除の際は、まず乾いた布で軽くほこりを払い、次に水で全体を流してから柔らかいスポンジやタオルで丁寧に拭きましょう。
● 掃除は「乾拭き→水洗い→柔らかい布で拭き取り」の順
● 彫刻部分には歯ブラシや絵筆などの柔らかい素材を使用
● 洗剤は原則不要。使う場合も中性または墓石専用洗剤を使用
研磨スポンジや酸性・塩素系の洗剤は、墓石に細かな傷をつけてしまい、そこから劣化が進む原因になります。
掃除の基本は「やさしく・こすらず・水で落とす」。この“3原則”を守ることで、お墓を長く美しく保つことができます。
コンクリート墓には専用洗剤や重曹を活用
沖縄では戦後に多く建てられたコンクリート製のお墓も一般的です。広い敷地に建てられたこのタイプは、雨風や湿気の影響を受けやすく、苔・カビ・水垢・鳥の糞などの汚れが目立ちやすい傾向にあります。
● 表面の汚れは水洗い→柔らかめのブラシでこする
● 頑固な汚れには重曹やセスキ炭酸ソーダを薄めて活用
● それでも落ちない場合は、コンクリート専用クリーナーを使用
重曹などは自然由来で扱いやすく、表面を傷つけにくいため便利です。ただし、酸性の洗剤(例:サンポール、ワイドハイター)はコンクリートの劣化を招くため避けましょう。
また、ひび割れがある場合は、掃除のついでに状態のチェックを行い、必要であれば専門業者に補修を依頼することも大切です。
・【沖縄のお墓】コストを押さえる石材選び、5つのポイント
沖縄のお墓掃除で使える道具と便利グッズ

沖縄のお墓は広く、草木も茂りやすいため、掃除道具はしっかり準備しておくことが大切です。とくに個人墓地では敷地内の清掃もすべて自分たちで行う必要があるため、効率的な掃除のための道具選びが仕上がりを左右します。
ここでは、墓石・コンクリート墓どちらにも使える基本の掃除道具と、草刈りや砂利掃除に役立つ便利グッズをご紹介します。
基本セット|軍手・スポンジ・柔らかいブラシなど
お墓掃除の基本アイテムは、お墓の材質を傷つけず、しっかり汚れを落とせる柔らかい素材がポイントです。
● 軍手(滑り止め付きがおすすめ)
● 柔らかいスポンジや雑巾
● 吸水性の良いタオル(複数枚)
● 絵筆・綿棒・歯ブラシ(細部用)
● ほうき・ちり取り・ゴミ袋
● バケツ・柄杓・水筒(個人墓地では必須)
特に墓石を乾拭きするための柔らかい布は必須アイテムです。雑巾も複数枚用意し、濡拭きと乾拭きで使い分けると、より丁寧な仕上がりになります。
便利道具|雑草バイブレーターや三角ホーとは?
沖縄のお墓は草木が繁りやすく、雑草取りが最も重労働だという声も少なくありません。最近では、こうした作業を効率化する便利道具も多く登場しています。
● 雑草バイブレーター:振動で根から抜く電動草抜き機
● 三角ホー:立ったまま草をかき取れる便利な鍬
● モンブラン草取り:墓石の隙間用のコンパクト草抜き
● 鬼の爪:砂利の中から雑草をかき出す専用ツール
また、砂利が敷かれたお墓ではザルを使って落ち葉と砂利を分別するのもおすすめです。掃除の負担を減らす道具を活用すれば、高齢の方や女性・子どもでも無理なく作業ができます。
やってはいけない!お墓掃除のNG行動

お墓掃除は、ご先祖様を敬い、感謝を込めて行う大切な行事ですが、やり方を間違えると、かえってお墓を傷めてしまうことがあります。
特に沖縄の墓地は個人管理のコンクリート墓や御影石の墓石が多く、それぞれに合った掃除法を知らないまま行うと、表面が劣化したり、汚れが染みついてしまうことも。
ここでは、お墓掃除の際に「やってはいけないこと」=NG行動と、その理由について詳しくご紹介します。正しい供養の“形”を守るためにも、ぜひ一度確認しておきましょう。
メラミンスポンジ・酸性洗剤は厳禁
墓石やコンクリート墓の掃除で特に注意したいのが、使用する洗剤や掃除用具の選び方です。清掃グッズとして人気の「メラミンスポンジ」は、実はお墓掃除には不向きなアイテムの代表例です。
● メラミンスポンジは研磨力が強く、石材表面を削ってしまう恐れがある
● 傷がついた部分から、雨水や汚れが染み込みやすくなり、劣化の原因に
● 強酸性・強アルカリ性の洗剤は、墓石の変色や白華現象を引き起こすことも
とくに避けたい代表的な洗剤例は以下の通りです。
● サンポールなどの酸性クリーナー
● ワイドハイターなどの塩素系漂白剤
● 「水あかクリーナー」などの強アルカリ製品(※未確認使用は避ける)
沖縄の高温多湿な気候では、墓石が劣化しやすいことから、刺激の強い洗剤や道具は使わないことが長持ちの秘訣です。使用するなら、墓石専用クリーナーまたは中性洗剤を水で薄めたものにしましょう。
墓石を傷つけないための注意点
お墓を掃除する“こと”自体はとても良い行いですが、掃除の仕方を間違えると逆効果になってしまいます。とくに墓石に傷をつけてしまうと、そこからカビや水分が侵入し、長年かけて劣化を招く恐れがあります。
● 強くこすらず、柔らかい布やスポンジで優しく洗う
● 彫刻部分は歯ブラシや絵筆など柔らかいもので細かく掃除
● 汚れが落ちにくい場合も、力任せにこすらずぬるま湯でふやかす
● 洗剤を使う場合は、必ず十分に水で流し、拭き取り乾燥させる
また、掃除のあとに水分をしっかり拭き取らないと、石材の内部に水が残り、カビやシミの原因にもなります。乾いたタオルでの仕上げの乾拭きも忘れずに行いましょう。
お墓掃除の意味と沖縄の“神”との関わり

お墓掃除とは単なる清掃ではなく、「供養」と深くつながる行為です。
特に沖縄では、ご先祖様や祖霊を敬う文化が今も色濃く残っており、掃除を通じて神聖な空間を整えることが、信仰と感謝のあらわれとされています。
沖縄のお墓には、墓石や敷地そのものを守る“神”の存在も意識されており、掃除やお参りの際には、まず神様に挨拶するのが伝統的な作法です。
ここでは、沖縄ならではのお墓掃除の“意味”と、それがどう「神」と関わっているのかを詳しく解説します。
ヒジャイガミ(左神)とは?沖縄の拝み文化に見る信仰のカタチ
沖縄のお墓掃除では、墓地に足を踏み入れる前に「ヒジャイガミ(左神)」へ手を合わせるのが基本です。
ヒジャイガミとは、お墓の左手(向かって右側)に鎮座し、その土地とお墓を日々守護してくれている“神”のこと。
● 墓地の守護神であり、掃除や参拝の際には必ず最初に拝む
● ヒラウコー(線香)や花米、酒、水、シルカビなどを供える
● 掃除や作業に入る「許可を得る」意味合いがある
このような拝み文化には、「掃除=神聖な場を整える儀式」という側面があり、ヒジャイガミへ挨拶をしないまま作業を始めるのは無礼とされることもあります。
また、ヒジャイガミが鎮座する「左側」は、沖縄の信仰において非常に重要な場所であり、“神が通る道”とも言われます。
そのため、生身の人は右側から入るべきという「通り道」の意識ともつながっています。
“掃除すること”が先祖供養に繋がる理由とは?
お墓を掃除する“こと”には、単に汚れを落とすという行為以上に、ご先祖様への感謝と敬意を形にする意味があります。
● 掃除を通じて、日常では向き合えない「命」や「血のつながり」を再確認する
● 体を動かすこと自体が、供養の一環としての“実践”となる
特に沖縄では、「手間をかけること」がご先祖への愛情表現とされてきました。
重箱料理を準備したり、掃除や草刈りを丁寧に行うことも、その一部です。
また、掃除を済ませた後に供物を整えてお参りする流れには、「神聖な場に感謝と祈りを届ける準備が整った」という意味合いもあります。
掃除する=供養する、という意識は、沖縄の御願文化の根幹とも言えるでしょう。
お墓掃除のタイミングはいつ?年間の主な行事と日程

沖縄では、お墓掃除のタイミングは「いつでも良い」というよりも、年中行事とセットで行うのが一般的です。
ご先祖様を迎える清明祭(シーミー)や旧盆、お彼岸などの前には、墓地をきれいに整え、ご先祖様を迎える“準備”として掃除を行います。
本州のように頻繁にお墓参りをする文化とは異なり、沖縄では特定の節目に集中的に掃除・供養を行うスタイルが根づいています。
ここでは、年間を通じてお墓掃除を行う代表的な行事や、代行サービスを利用する際のタイミングをご紹介します。
清明祭(シーミー)や旧盆(お盆)、お彼岸などの行事前
沖縄のお墓掃除の主なタイミングは、以下の年中行事の直前です。
● シーミー(清明祭)前
→ 春の先祖供養行事。2025年は4月4日〜19日頃
● 七夕(旧暦7月7日)前
→ 旧盆の案内として宗家が訪れる。2025年は8月29日(金)
● 旧盆(ウンケー〜ウークイ)前
→ ご先祖様を迎える三日間。2025年は9月4日(木)〜6日(土)
● 秋のお彼岸(フカマチヒングァン)前
→ 地域によってはお墓参りの風習も。2025年は9月20日(土)〜26日(金)
これらのタイミングの1週間前〜前日までに掃除を終えるのが理想です。
また、旧盆と秋のお彼岸が近い年(2025年など)は、旧盆に向けて掃除→お彼岸にもお参りという流れがスムーズです。
地域や家によっては、「旧暦16日(ジュールクニチー)」や「トーカチ(88歳祝い)」などの節目でも掃除を行うことがあります。
・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー
・【沖縄の御願】秋の彼岸は旧暦8月。沖縄の供え物と拝み方
代行サービスを使う場合の時期と費用相場
高齢化や遠方在住の影響もあり、お墓掃除の代行サービスを利用する家庭も増えています。
特に旧盆やシーミーなどの行事前は依頼が集中するため、早めの予約が肝心です。
● 依頼は行事の2〜3週間前までが安心
● 特に8月下旬〜9月初旬(旧盆前)は混雑
● 作業内容や写真報告付きのプランが主流
● 一般的な個人墓地:30,000円〜40,000円前後
● 小規模な霊園墓地:15,000円〜25,000円前後
※広さや雑草の量、オプション(供え物・拝み)によって変動あり
全国平均よりやや高めですが、これは沖縄のお墓が広く、雑草除去などの手間が多いことが関係しています。
また、年に複数回お願いする場合は、定期清掃プランや年間契約を検討するのもおすすめです。
「どうしても行けない…でもきちんと供養はしたい」そんな時こそ、信頼できる代行業者の活用が心強い選択肢となります。
まとめ|心を込めた掃除が供養の第一歩

沖縄のお墓掃除は、ご先祖様への感謝を表す大切な供養の一つです。
ヒジャイガミ(左神)への御願や、右側から入る作法など、沖縄独自の神聖な意味が込められた文化も特徴です。
特に2025年の旧盆や七夕、シーミー、お彼岸などの行事前は、お墓をきれいに整える絶好のタイミングです。
掃除を通じて、神やご先祖様への敬意をあらためて形にしてみてはいかがでしょうか。
関連記事
合わせて読みたい




人気記事ランキング
 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説
旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!
【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談
親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ
老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説
【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー
一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは
夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識
ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説
【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③
沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③
カテゴリ













































