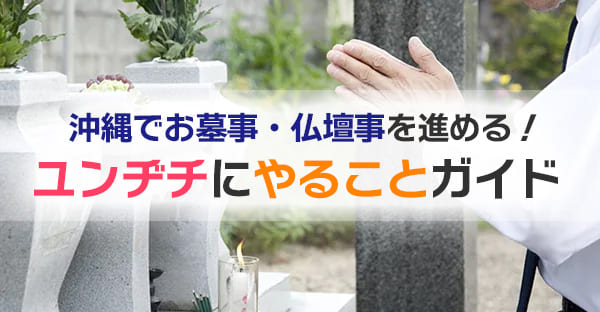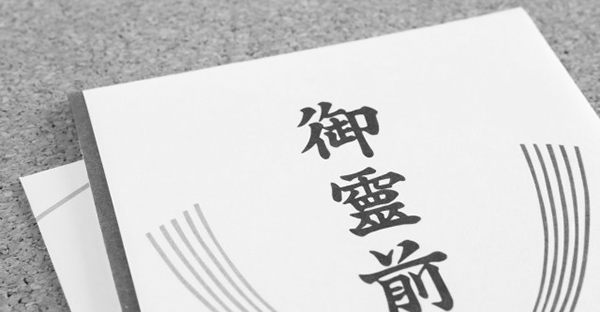沖縄の供え花マナー|お彼岸・お盆・法要にふさわしい花の選び方
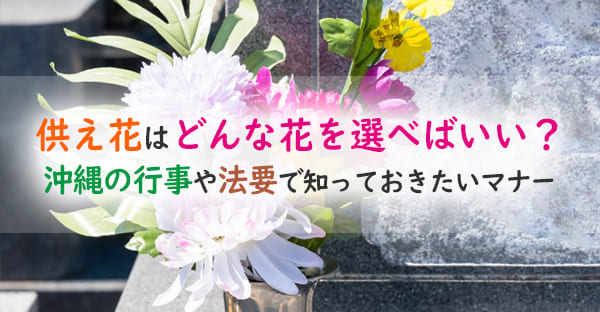
供え花は、先祖への感謝や祈りを形にする大切な供養の一つです。お彼岸やお盆、法要などの節目には、それぞれの場にふさわしい花を選ぶことが求められます。
一般的なマナーは全国共通ですが、沖縄にはジュールクニチー(十六日祭)やシーミー(清明祭)、タナバタなど独自のお墓参り行事があり、季節に応じた供え花を用意する習慣も見られます。
本記事では、全国的な基本マナーとあわせて、沖縄の行事に合わせた供え花の選び方をわかりやすく紹介します。
目次
供え花の基本マナー

供え花は、ご先祖や故人に感謝や祈りを伝えるために欠かせない供養の一つです。
きれいな花を供えることで、場を清め、心を落ち着ける役割も果たします。まずは供え花の基本的な意味と、選ぶ際に気をつけたいポイントを確認しましょう。
供え花の役割と意味
供え花は単なる飾りではなく、「故人やご先祖への感謝と追悼の気持ち」を表す大切な供養の形です。
花の香りや色合いには心を和ませる力があり、供養の場を明るく整える役割もあります。
また、四季の花を供えることで「自然の恵みを分かち合う」という意味も込められています。お彼岸やお盆、法要の際に供え花を欠かさないのは、こうした背景があるためです。
避けたい花や色合い
供え花を選ぶ際には、場にふさわしくない種類や色合いを避けることが大切です。
棘のあるバラや、毒を持つ彼岸花は一般的に供花には不向きとされています。また、派手すぎる原色や濃い香りの花も避けた方が無難です。
基本的には、白や淡い色合いの花を中心に選ぶと落ち着いた雰囲気になります。地域や宗派によって違いもありますが、故人や参列者に不快感を与えない「清らかさ」を意識して花を選ぶことが供養のマナーです。
お彼岸にふさわしい供え花
お彼岸は、春分・秋分の日を中心とした7日間に行われる先祖供養の行事です。
この時期には仏壇やお墓に供え花を飾り、ご先祖に感謝の気持ちを伝えるのが習わしとなっています。
供え花は単なる飾りではなく、祈りを形にする大切な供養の一つです。ここではお彼岸にふさわしい花や選び方の基本を紹介します。
・沖縄の秋彼岸の過ごし方。2025年はいつ?お供えと地域の違い
定番の花とその意味
お彼岸に供える花は、清らかさや落ち着きを感じさせるものが好まれます。
特に菊は長持ちし、「高貴」「誠実」を意味することから定番中の定番とされています。そのほかにも、お彼岸に選ばれる花には次のようなものがあります。
● カーネーション:感謝の気持ちを伝える花
● リンドウ:誠実・正義を意味し、秋のお彼岸に出回りやすい
● スターチス:変わらぬ心を表し、日持ちの良さが特徴
これらはどれも季節に合わせて選びやすく、見た目の美しさだけでなく意味合いも供養にふさわしいものばかりです。特に菊は地域を問わず安心して選べる花といえるでしょう。
色の選び方と注意点
供え花の色合いは、白や紫など落ち着いた色を中心にまとめるのが基本です。
白は清浄、紫は尊厳を意味し、供養にふさわしいとされています。赤や黄色を取り入れる場合も、淡い色合いを選ぶと落ち着いた印象になります。
反対に、真っ赤な花や派手すぎる色合いは供養の場には不向きです。
また、棘のある花や強い香りの花も避けた方がよいでしょう。華やかさよりも「清らかで落ち着いた雰囲気」を意識して花を選ぶことが、お彼岸の供え花マナーの基本です。
お盆にふさわしい供え花

お盆はご先祖の霊を迎え、感謝を伝える大切な年中行事です。
供え花はお墓や仏壇を彩り、祈りの気持ちを形にする役割を持っています。全国的に共通するマナーを押さえつつ、花に込める想いを意識して選ぶことが大切です。
全国のお盆と供花の基本
◇お盆に供える花は、清浄さや落ち着きを感じさせるものが基本です。
特に暑い時期に行われるため、日持ちの良さも重要なポイントになります。代表的に選ばれる花には次のようなものがあります。
● リンドウ:誠実を象徴し、夏から秋にかけて出回りやすい
● トルコキキョウ:柔らかな色合いで、清らかさと優しさを表す
● スターチス:色持ちがよく、「変わらぬ心」を表す
これらは全国的に広く親しまれており、花屋でも手に入りやすい品種です。清楚で日持ちの良い花を選ぶことが、お盆の供花にふさわしいとされています。
供花に込める想い
お盆の供花は単なる飾りではなく、「ご先祖への感謝」と「家族の安寧を祈る気持ち」を込めるものです。
派手すぎない落ち着いた色合いの花束やアレンジにすることで、祈りの気持ちが伝わりやすくなります。供花はご先祖を敬う心を表現するものですから、形式にとらわれるよりも「感謝の心をどう花に込めるか」を大切に選ぶとよいでしょう。
法要・法事の供え花マナー
法要や法事の場では、供え花の種類や色合いにも配慮が求められます。節目ごとにふさわしい花を選ぶことで、故人を偲ぶ気持ちがより丁寧に伝わります。
四十九日・一周忌など節目ごとの花の選び方
法要の供え花は、時期によってふさわしい花や色合いが異なります。特に四十九日までは「喪に服す期間」とされ、落ち着いた花が選ばれます。
…白や淡い紫の菊、ユリ、カーネーションなど落ち着いた色合いの花
● 一周忌・三回忌:
…白を基調にしつつ、淡いピンクや黄色を加えた花で柔らかさを出す
● 七回忌以降:
…色の制限は少なくなり、明るい色合いも取り入れてよい
このように、節目に合わせて花の雰囲気を調整することが、故人を偲ぶ心を伝えるマナーになります。
・沖縄のスーコー(焼香)。本州出身者が分かる5つの解説
色合いと本数の基本ルール
供え花は「落ち着いた色合い」と「偶数ではなく奇数本」を基本とするのが一般的です。白・紫・淡いピンクなどを組み合わせると、清らかでやさしい雰囲気になります。
● 紫:尊厳・高貴を表す
● 淡いピンクや黄色:やさしさ・感謝を表す
また、供花は奇数本でまとめるのが一般的で、3本、5本、7本などが好まれます。偶数は「割れる」を連想させるため避けられることが多いです。こうした基本ルールを守ることで、法要や法事にふさわしい花を選ぶことができます。
沖縄のお墓参り行事と供え花

◇沖縄では本土の彼岸やお盆に加え、旧暦に基づいた独自のお墓参り行事があります。
代表的なのはジュールクニチー(十六日祭)、シーミー(清明祭)、タナバタ(七夕)の三大行事です。
いずれも先祖を敬い感謝を伝える大切な供養の機会であり、花を供えることにも意味があります。ここでは、それぞれの行事にふさわしい供え花を紹介します。
ジュールクニチー(十六日祭)に供える花
旧暦1月16日に行われるジュールクニチーは「あの世の正月」と呼ばれ、特に離島地域で盛んに行われてきました。
新しい年を迎えたご先祖に挨拶をする日であり、供え花も清らかな白や淡い色が基本です。菊やカーネーションなど、長持ちして落ち着いた印象の花が好まれます。正月行事の一つでもあるため、あまり派手にならないよう心掛けるとよいでしょう。
・ジュールクニチ(十六日)☆離島地域に多いお墓参り行事
シーミー(清明祭)に供える花
4月頃に行われるシーミーは、一族が墓前に集まり、重箱料理を広げて賑やかに過ごす、お祝い要素を持つお墓参り行事です。
供え花は明るさを意識し、白や紫を基調にしつつ、淡いピンクや黄色を加えて華やかさを出すのがおすすめです。春の花である菊やカーネーションに加え、季節の花を取り入れると場が和みます。
・沖縄の秋彼岸の過ごし方。2025年はいつ?お供えと地域の違い
タナバタ(七夕)に供える花
◇旧暦7月7日のタナバタは、旧盆を迎える前にご先祖に挨拶をする行事です。
ご先祖へ「旧盆のお迎えの報告」をする意味合いが強いため、落ち着いた雰囲気の花が適しています。白い菊やリンドウなどを中心に選び、控えめで清楚な印象にまとめるとよいでしょう。
・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識
沖縄の旧盆に供える花
沖縄の旧盆(ウンケー・ナカヌヒ・ウークイ)は、ご先祖を迎え、共に過ごし、送り出す三日間の行事です。
供え花には特別な決まりはなく、全国と同じように白や紫を基調にした菊やトルコキキョウ、カーネーションなどが一般的です。最終日のウークイには、果物や重箱料理と一緒に供花を整え、ご先祖を丁寧に送り出します。
・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー
彼岸に供える花(沖縄編)
◇沖縄でも春と秋の彼岸は先祖供養の大切な期間です。
…沖縄でお彼岸の先祖供養は、仏前供養と屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)を行う家庭が多いでしょう。
本土と同様に菊を中心にした落ち着いた花が用いられますが、気候の影響で南国の花が選ばれることもあります。ユリやランなど、日持ちが良く見栄えのする花を取り入れると、お彼岸の供養にふさわしい供え花となります。
・沖縄のお彼岸は本州と違う?風習・供え物5つの違い【2025年版】
供え花を贈るときの注意点

◇供え花は自宅で供えるだけでなく、法要や法事の際に贈ることもあります。
その場合は、贈り方やマナーに注意しないと失礼にあたることもあります。ここでは花屋への依頼方法や立札の書き方、届けるタイミングなどを整理します。
花屋へ依頼する際のポイント
供え花を花屋に注文する場合は、法要やお盆など用途を伝えることが大切です。
「法要用」「お供え用」と伝えると、適した花の種類や色合いでアレンジしてもらえます。花の種類や色に迷う場合も、プロに相談すれば安心です。
また、仏式・神式・キリスト教式など宗教によって花の選び方が異なるため、事前に確認しておくと間違いがありません。
立札やメッセージのマナー
◇供え花には立札やメッセージカードを添えることがあります。
立札には「○○家一同」「親戚一同」「株式会社○○」など贈り主の名前を明記します。故人名を記載する必要はなく、あくまで「誰から贈られた花か」を伝えるのが目的です。
メッセージカードを添える場合は「ご冥福をお祈りいたします」「安らかな眠りを」など、簡潔で丁寧な言葉を選びましょう。
配送・持参のタイミング
◇供え花を贈るタイミングは、法要・法事が始まる前までに届けるのが基本です。
…自宅へ届ける場合は前日、会場へ送る場合は当日の朝までに届くよう手配しましょう。
直接持参する場合は、式が始まる前に静かにお供えします。お彼岸やお盆の供花の場合も、初日の前後に合わせて準備すると安心です。
タイミングを誤らずに手配することが、供養の場にふさわしい供花の贈り方です。
・葬儀で使う花の基本。準備をする際に必要な基礎知識
まとめ|供え花で気持ちを伝える供養

供え花は、お彼岸やお盆、法要などの節目にご先祖や故人へ感謝を伝える大切な供養の形です。白や淡い色を基調にした花を選び、場に応じた落ち着きや清らかさを意識することが基本のマナーとなります。
沖縄ではジュールクニチー、シーミー、タナバタといった独自のお墓参り行事がありますが、どの場面でも「心を込めて花を供える」という気持ちは変わりません。形式にとらわれすぎず、感謝や祈りを込めて花を選ぶことこそが、最も大切な供養につながるでしょう。
・沖縄のお墓参りマナー|時間・服装・霊園ルールと本州との違い
・納骨堂でのお参りマナー|彼岸・お盆に知っておきたい供養の基本
関連記事
合わせて読みたい