沖縄の旧暦行事『ヨーカビー』と『シバサシ』とは?火の玉・魔除けの風習を解説
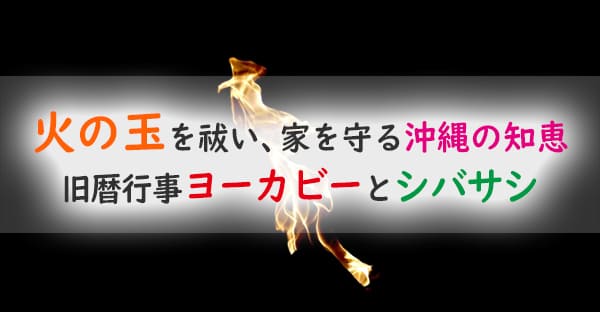
沖縄の旧暦8月は、悪霊祓いや魔除けの行事が集中する特別な時期です。その代表が「ヨーカビー」と「シバサシ」。
夜空に浮かぶ火の玉を祓うヨーカビー、そしてススキや桑で作ったシバを家の四隅に差して結界を張るシバサシは、古くから家庭や集落を守ってきました。
本記事では、ヨーカビーやシバサシの意味や由来、現代に伝わる風習まで詳しくご紹介します。
目次
沖縄の旧暦8月に行われる悪霊祓い行事

ヨーカビーとシバサシの位置づけ
◇旧暦8月は、沖縄で「魔物が出やすい月」と言われてきました。
旧盆が終わった後、先祖とともにやってきた無縁仏や悪霊がさまようと考えられたためです。そこで各家庭や集落では、悪霊祓いのために「ヨーカビー」と「シバサシ」という行事を行ってきました。
ヨーカビーは夜に火の玉を確認し、爆竹や祈願で不吉を祓う行事。一方のシバサシは、ススキや桑を束ねた「シバ」を家の四隅や門に差して結界を張り、魔物の侵入を防ぐ行事です。
どちらも古くから受け継がれてきた、沖縄独特の悪霊祓いの知恵といえるでしょう。
旧暦行事が集中する理由
旧暦8月は、稲や小豆の収穫を迎える大切な時期であると同時に、台風や疫病などの災いが訪れやすい季節でもありました。
そのため沖縄では、この時期に悪霊やまじむんを遠ざける行事が集中しています。
ヨーカビーやシバサシはもちろん、赤カシチーを供える「八月カシチー」なども同じ時期に行われ、家庭や地域の安心と無病息災を祈ってきました。
こうした連続した行事は、自然と共に暮らす中で災いを避け、豊かな実りを願う人々の生活の知恵でもあります。
・2025年10月 沖縄旧暦カレンダー|カジマヤーと大綱引き、秋の伝統行事まとめ
ヨーカビー(八日日)とは

火の玉(タマガイ・イニンビー)の言い伝え
ヨーカビーは、旧暦8月8日頃に行われる悪霊祓いの行事で、別名「八日日(ようかび)」とも呼ばれます。
火の玉が上がる家は、近いうちに不幸が訪れるとされ、村人は高台から集落を見渡し、不吉な兆しを見張ったと伝えられます。こうした言い伝えは、沖縄独特の死生観や霊的な感覚を今に伝えています。
爆竹や祈願で悪霊を祓う風習
火の玉を確認した家では、悪霊や不吉を払うために爆竹を鳴らしたり、ユタ(霊的な力を持つ民間巫者)を呼んで祈願をしたといわれています。
爆竹の大きな音には魔物を追い払う力があるとされ、夜の集落に響く音は厄払いの象徴でした。また、ヨーカビーの祈願には「3年以内に死者を出さないように」という切実な願いが込められており、地域の人々にとっては暮らしを守る大切な行事でした。
現代に残るヨーカビーの形
現代の沖縄では、夜間も街灯が明るく、火の玉を見張る風習はほとんど行われなくなりました。爆竹も騒音の問題から姿を消しています。
しかしその代わりに、家庭で手を合わせたり、ヒヌカン(火の神)へ祈願する形でヨーカビーを続ける家があります。
また、門前で花火を楽しみながら「ヨーカビーの日」を意識する家庭もあり、不吉を祓うと同時に、ご先祖や精霊への慰霊の意味を込めて受け継がれています。
・ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識
シバサシ(柴差し)とは

ススキと桑で作る「シバ」の意味
◇シバサシは旧暦8月9日から11日頃に行われる魔除けの行事です。
「シバ」とは、ススキや桑の枝を束ねて作ったものを指します。ススキは稲に似て繁殖力が強く、また葉先が鋭いため「剣」の象徴とされ、魔物を寄せつけない力があると考えられてきました。
一方の桑は「害を避ける木」とされ、雷除けの言い伝えとも結びついています。これらを組み合わせたシバは、強い魔除けの呪具として沖縄の人々に用いられてきました。
家や門にシバを差して結界を張る
シバサシでは、このシバを家の四隅や門、屋敷の出入口、さらには家畜小屋や倉庫の隅に差し込みます。
旧暦8月は災いや疫病が広がりやすい時期とされ、シバサシを行うことで家族や財産を守ろうとしたのです。現代の住居では大きなシバを差すのは難しいため、小さなシバを玄関や室内に飾る家庭も増えています。
サン・ゲーンなど魔除け道具の種類
◇シバサシで用いられる魔除け道具にはいくつか種類があります。
もっとも一般的なのは、ススキの葉を束ねた「サン」で、弁当や料理に添える小型の「サングァー」もあります。
さらに、桑の枝を加えて作る「ゲーン」はより強力な魔除けとされ、特に旧暦8月のシバサシでは多く用いられます。これらは数や結び方にも意味があり、3本束ねることで呪力が増すと信じられてきました。
サンやゲーンを差す場所に制限はなく、守りたい対象があればどこにでも差してよいとされる点も特徴的です。
・沖縄でお通夜前に行いたいヌジファとは。家族で行う儀礼
八月カシチー(ハチグヮチカシチー)と赤カシチー

シバサシと同日に行われる御願
シバサシと同じ旧暦8月10日前後には「八月カシチー(ハチグヮチカシチー)」と呼ばれる御願も行われます。
これは収穫を迎えた米や小豆に感謝し、家族の無病息災を祈る行事です。六月に行われる「六月カシチー(白いおこわ)」に対し、八月は赤いおこわを用いるのが特徴です。
赤い色には邪気を払い、魂を強める意味が込められており、シバサシとあわせて行うことで「結界を張る」だけでなく「繁栄と健康を祈願する」役割を担ってきました。
赤カシチーの供え方(仏壇とヒヌカン)
八月カシチーでは、炊き上げた赤カシチー(赤飯)を仏壇とヒヌカン(火の神様)の両方に供えます。
ヒヌカンには箸を添えず、赤カシチーのみをお供えします。
一方、仏壇には赤カシチーに加えてお膳を整えるのが一般的で、汁物や酢の物(ウサチなど)を添える家庭も多いです。
赤飯は家族で分かち合うことで「マブイ(魂)を強める」とされ、御願の後には皆でいただく習わしもあります。現代ではスーパーや家庭で手軽に赤飯を用意できるため、生活に根差したかたちで受け継がれています。
・沖縄の旧暦行事「八月カシチー」とは?赤カシチーのお供えと拝み方を解説
・沖縄の大綱引き2025年版|日程・見どころ・歴史と参加方法を徹底解説
イニンビー(遺念火)の伝承

沖縄に伝わる火の玉の昔話
◇沖縄には、夜道に火の玉が浮かぶという不思議な言い伝えが数多く残されています。
この火の玉は「イニンビー(遺念火)」と呼ばれ、成仏できずに恨みや未練を残した魂が姿を変えたものとされています。
たとえば首里の識名坂では、悲劇の末に亡くなった夫婦の魂が夜ごと二つの火の玉となって現れると語り継がれてきました。
伊江島や北谷など各地にも似た伝承があり、愛する者を残して亡くなった人々の哀しみが、火の玉となってさまよう姿として描かれています。
こうした昔話は、沖縄の人々にとって火の玉が身近で、霊的存在を恐れつつも畏敬の念を抱いてきた証といえるでしょう。
悪霊祓いと慰霊、二つの意味合い
◇イニンビーは不吉の前触れとされ、ヨーカビーで悪霊を祓う対象にもなりました。
しかし一方で、愛情や想いを残してこの世に現れた魂と捉え、慰霊の対象とする地域もあります。火の玉を「まじむん(魔物)」と恐れるだけでなく、「故人の声なき願い」として受け止めることで、踊りを奉納する集落もあったと伝えられます。
つまり、イニンビーには「祓うべきもの」と「慰めるべきもの」という二つの側面があり、沖縄の死生観の奥深さを今に伝えています。恐れと同時に祈りを込めて向き合う姿勢が、ヨーカビーやシバサシの行事に息づいているのです。
・沖縄メモリアル整備協会|沖縄の昔話
まとめ|ヨーカビーとシバサシで家族の無病息災を願う

ヨーカビーとシバサシは、旧暦8月に行われる沖縄独特の悪霊祓いの行事です。
ヨーカビーでは火の玉を祓い、シバサシでは家の四隅に結界を張って魔物の侵入を防ぎます。さらに、赤カシチーを供える八月カシチーとあわせて行うことで、家族の健康や豊かさを願う意味合いも込められてきました。
これらの行事は、不吉を遠ざけるだけでなく、先人の魂を慰め、自然と共に暮らしてきた人々の知恵でもあります。
現代では形を変えながらも、火の玉や魔除けの伝承は地域や家庭に受け継がれています。ヨーカビーとシバサシを通して、家族の無病息災を祈る心は、今も変わらず大切にしたい沖縄の文化といえるでしょう。
・観音様は子どもの守護神☆観音巡り8つの拝所【2019年2月20日更新】
関連記事
合わせて読みたい
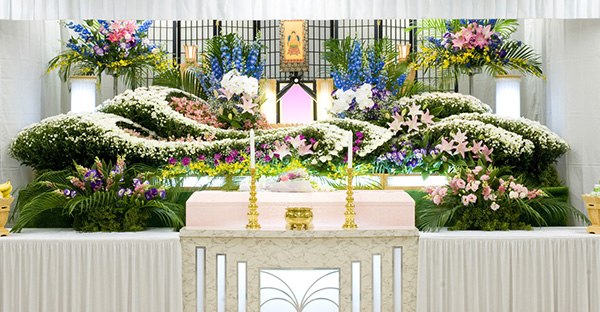



人気記事ランキング
 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説
旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!
【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談
親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ
老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説
【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー
一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは
夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識
ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説
【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③
沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③
カテゴリ













































